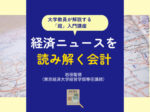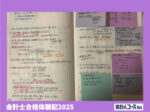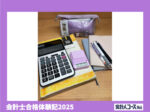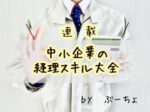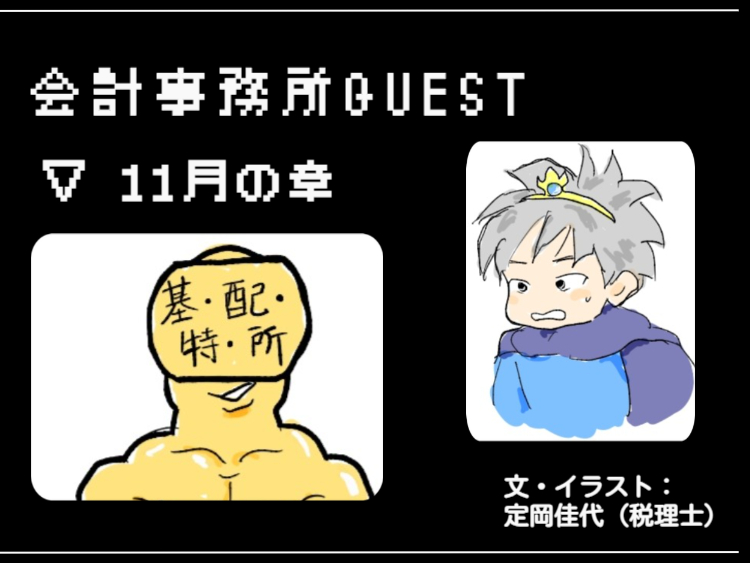
今年ももう残すところあと2ヶ月。そろそろ年末調整の準備を始める時期になりました。
10月中に年末調整の資料を発送している事務所もあるそうですが、みなさん準備のほうはいかがでしょうか?
今回のテーマは、「年末調整のちょこっとQ&A」です。
ますます複雑になる年末調整…会計事務所にとって、年末調整はまるで年々レベルアップしていく魔物のように感じられるのではないでしょうか。
憂うつな年末調整を迎える前に、おさらいの意味も兼ねて、ちょっとしたQ&Aをピックアップしてみました。
それではさっそく、みていきましょう!

Q1. 年末調整の対象となる給与はいつからいつまで?
A1. 甲欄の従業員で1月1日から12月31日までに支給される給与です。
年末調整の対象となる給与は、当社をメインの勤め先としている甲欄の従業員で、「支給日」が1~12月のあいだに到来している給与です。
たとえば、給与の支給日を「当月末日締め翌月20日支給」としている場合、12月分の給与は翌年1月20日支払いですから、今年の年末調整の対象とはなりません。
また、年の中途で退職している従業員は基本的に年末調整の対象外ですが、12月支給のあと年末近くに退職した従業員は年末調整の対象となります。
なお、年間の給与総額が2,000万円超の従業員は対象外となり、確定申告をしていただく必要があります。

Q2. 乙欄の従業員は「扶養控除申告書」(マルフ)を提出しなくていいですか?
A2. 乙欄の従業員は提出義務はありませんが、「乙欄であること」を把握しておいた方がよいでしょう。
乙欄とは、「2箇所以上の勤め先があり、当社が主たる勤め先ではない」という従業員が該当します。乙欄の従業員は他のメインの会社で年末調整を行うため、扶養控除申告書の提出は不要です。
ただ、うっかり扶養控除申告書を提出し忘れる甲欄の従業員がいるかもしれないため、扶養控除申告書の提出の有無とは別に、「この従業員は甲欄/乙欄である」ということを把握しておいた方が、お客様(顧問先)にとっては親切に感じられるかもしれません。
大人数の会社の場合は、「甲欄/乙欄のリスト」をいただくなど工夫をして、年末調整対象者の漏れがないようにしておきましょう。

Q3. 令和7年度から住宅ローン控除の「調書方式」というのを受けたのですが、まだ届きません。
A3. 調書方式による「年末残高調書」が届くのは電子の場合11月中旬以降です。
確定申告により住宅ローン控除の適用を受けた人は、その翌年から一定の資料を提出することで、年末調整のみで住宅ローン控除を受けることができます。
控除を受けるための添付資料の一つである「住宅借入金の年末残高証明書」は、従来は金融機関等から交付を受けていましたが(証明書方式)、税務署から電子または書面で提供される「年末残高調書」を添付する方法(調書方式)も選択できるようになりました。(ただし調書方式は現状、一部の金融機関に限ります)
ここで懸念されるのは、調書方式による交付時期が11月中旬以降で、早期に年末調整資料を回収したい場合には、スケジュールがタイトになることです。
まだこの方式を受ける人は少ないかもしれませんが、このような改正があったということを覚えておきましょう。
(参考)
住宅ローン控除の適用に係る手続(年末残高調書を用いた方式)について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/jutaku/index.htm

Q4. 配布されたマルフやマルホの裏面の文字が小さすぎて読む気が起こりません。
A4. すべて読むのは至難の業ですよね・・・。記入事項のポイントや添付資料を簡潔におさえておきましょう。
・前年と同じ資料を忘れずに添付しましょう。
(生命保険料・小規模企業共済等掛金・地震保険料などの控除(払込)証明書)。
・名前・フリガナ・郵便番号・住所を忘れず書きましょう(特に配偶者や子供のフリガナを忘れずに)。
・中途入社の方は(あれば)「前職の源泉徴収票」も添付しましょう。
・「合計所得金額」はアルバイト・パートだと年収から65万円ひいた金額。年収は現時点の見積りでOK。
あと、「年末調整の改正をもっと詳しく知りたい」というの職員の方もいらっしゃるかもしれません。
そんな方には、YouTubeの年末調整解説動画を紹介するのがオススメです。
いまはたくさんの税理士YouTuberの先生がわかりやすく配信してくれています。気に入った動画をピックアップしておき、ここぞというときに教えてあげると喜ばれると思います。

さいごに
制度改正へ対応することは会計事務所の使命です。
しかし、さすがに近年の所得税の改正は複雑すぎると個人的には感じております。顧問先の経理さんからの質問にいかにわかりやすく説明するか、考えるのに一苦労ですよね…。
今年も予想される質問攻撃に立ち向かわなくてはならない会計事務所のみなさんにとって、この記事が少しでも癒しになれば幸いです。
<著者紹介>
定岡 佳代(さだおか かよ)
税理士
兵庫県出身。1980年生まれ。神戸大学工学部建設学科、神戸大学大学院自然科学研究科(土木工学)修了。
関西で技術職に就くも、結婚・出産・上京を機に専業主婦に。次男の妊娠中に簿記の勉強を始め、日商簿記3級・2級に独学で合格。そこから税理士試験に挑戦し、パート勤務、大学院通学と並行しながら3科目合格。立教大学大学院経済学研究科を2020年3月に修了。2021年4月、税理士登録。
硬式野球男子2人の母。「税理士を目指すママ」コミュニティで知り合った友人のママ税理士4人で、セミナーや対談など活動をしている。都内の税理士事務所、税理士法人で約10年の修行を経て、2023年8月に独立開業。「お客様はピッチャー、私はキャッチャー。どんな球でも受け止める。」をモットーに、お客様との対話を大切にしている。