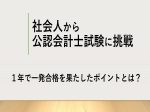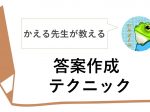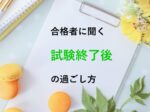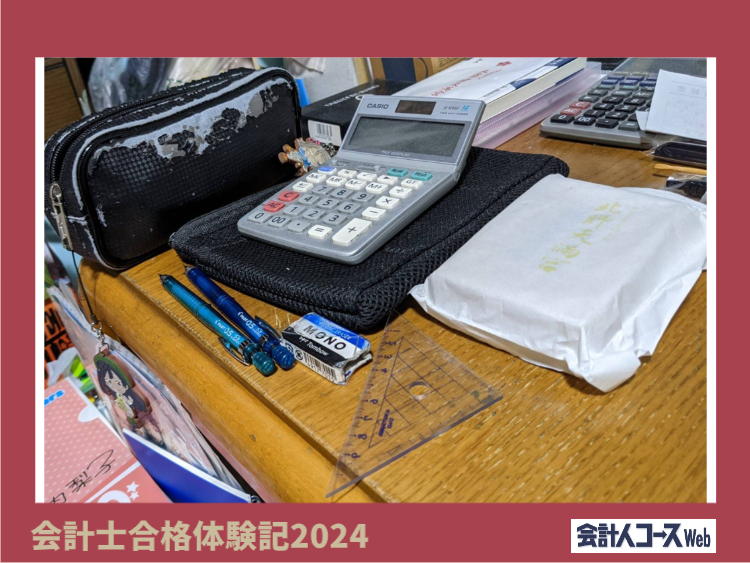
殿岡連
(22歳、法政大学4年)
〈受験情報〉
学習スタイル:CPA会計学院(通信)
▶トップ画像は殿岡さんの学習スペース(本人提供)
奨学金を借りたことがきっかけで、会計士に興味を持つ
私が会計士を目指したのは、多額の資金が動く企業を財務的な面から手助けしていきたいと考えたからです。
このように考えたのは、大学進学時に奨学金を借りたことと、会計士の仕事を知ったことがきっかけでした。
私は幼い頃から身近で困っている人を放っておくことができない性分であり、その影響から将来は人を助ける職業に就きたいと思っていました。
実際、大学も、人を助けることができる弁護士を目指して法政大学法学部に進学しました。
しかし、確かに弁護士は法律上において困っている人を助けることは可能ですが、時に罪を犯した人を無罪と主張し弁護することもあり、黒を白と言うことができない私には弁護士は不向きであると実感しました。
しかし、同時期、奨学金を借りたことで、私は大学進学等の重大なことを為すときには、多額の資金が必要となることを学びました。
そして、多額の資金が動く企業を支援できれば、企業やそこで働いている方々を助けることができると考えました。
そして、大学で開催された会計士セミナーで、会計士には多彩なキャリアプランがあり、多くの経験で得た知識・能力により問題を抱えている企業を助けることできることを知りました。
「会計士になれば、その企業をひいては企業で働く方々を助けられる」と確信しました。
このようにして、資金の重要性と会計士の使命を学び、企業の健全な発展を財務面から手助けしたいと思い、志しました。
具体的な学習方法や学習計画
1年目~2年目前半
まず、勉強を始めてから1年目~2年目前半は、とにかく財務会計論、管理会計論の計算を集中的に鍛えました。
この2科目は、会計士試験の代名詞であり、得点も財務会計論は他の科目の2倍となっています。
学習方法としては、テキストと問題集が一通り終わったら、総合問題をたくさん解きました。
総合問題では、複数の論点が出題されるため、頭から抜けている論点を確認できることはもちろん、特定の問題文に対してどの会計処理を使用するかを考えることになります。
会計処理に対する実践的な理解が深まりました。
この総合問題は、レギュラー答練、短答答練だけでなく、簿記1級過去問も利用すると演習量が増え効果的です(簿記1級の範囲は公認会計士試験と大幅に重なっている)。
また、計算に慣れてきた頃に、同時進行で上記2科目の理論も学習しました。
理論は難解に書かれているため、計算と絡めて理解しました。
計算を学習する時に少しの時間、同じ論点の理論のことも考えました。
2年目後半から
2年目後半に関しては企業法、監査論の割合を高めました。
短答においてこの2科目はインプットすることが多く、テキストのみを使用する方もいらっしゃると聞きますが、私は頭から抜けている論点や細かな論点を知るために問題集を多く使用しました。
短答本試験では細かな所まで出題されるためC論点も理解する必要があります。
論文に関しては、論点をアウトプットできるようにするためにとにかく暗記しました。
ここで、理解した上で覚えることが重要ですが、特定の会計処理に対して「なぜこのような理由になるのか」を深く言及するのではなく、「この理由によりそのような会計処理をするのか」と割り切り、少しでも多くの論点を覚えました。
また、多くの論点は類似性があるため、そのような類似性を見つけるように他の論点も考えながら特定の論点を学びました。
学習計画
学習計画に関しては、計画自体は予備校の進行表に沿って行いました。
日々の自習は各科目の答練で判明した自身の課題を積み上げ、その課題を解決するための時間や精神的な負担の軽重を考慮してから、1週間、そして1日にやるタスクの組合せを決めていました。
連続して負担の重いタスクを詰め込みすぎるとモチベーションが低下しまうため、長時間続けるために常に自身のキャパには注意していました。
経営学と管理会計は、少し遅れていたので優先的にしていました。
また、イレギュラーで重要論点がたまりすぎた場合には、1日中重要論点だけをやる日もつくりました。
塾講師のアルバイトとの両立
学生時代、私は塾講師のアルバイトをしていました。
大学進学時、私は今まで培ってきた勉強のスキルを生かして社会経験を積みたいと考え、塾講師のアルバイトを選択しました。
始めた当初は苦戦していましたが、数をこなすうちに多くの時間をアルバイトに使いたいと思いました。
しかし、同時期大学のセミナーで会計士を知り、将来会計士となり、企業を財政面からサポートしていきたいと思いました。
どちらもやりたいことであり、片方をあきらめることができなかったため、両立することを決めました。
中途半端に行うことは許されないことから、私は両立するために無駄な時間をつくらないように心がけました。
具体的には、バイト先への移動時間はその日に覚えた知識を復唱したり、一問一答を行っていたりしました。
さらに、入浴中にも必ずその日に覚えた論点を復唱しました。
論文に関しては、自身で考えて書くというよりも、自分が覚えている論点を組み合わせて回答するため、論点の復唱が重要になると感じています。
モチベーションの保ち方として、モチベーションが下がったときは何もしないと決めていました。
そのようなときに勉強をしても時間だけが過ぎていき、飽きてしまうため、休息をとるようにしていました。
休息をとることで、「明日は頑張ろう」と、モチベーションが復活しました。
受験期に知っておきたかった情報
会計士のキャリアの多彩さ
大学のセミナーで公認会計士は監査法人で監査に従事することや独立開業することなど、多くのことができると知ることが出来ました。
合格後の就活で英語を使った国際業務やデジタル人材によるIT監査、サステナビリティまでにも関与できることを知り、この情報も受験期に知っておきたかったと思いました。
特に英語に関して、大学の講義で英語もあったため、就職後のことも考えて、もっと英語について学んでおくべきだったと少し後悔しています。
就活の仕方や学生非常勤制度の存在
受験期は就活の仕方等を気にする必要はないですが、これらの情報を知っておくことで受験のモチベーションが高まると思います。
特に学生非常勤制度に関しては、在学中に合格し、監査法人から内定を頂ければ、在学中に監査法人で働くことができ、そして高い給与を得ることができるため、大学生は知っておいたほうがよいと感じています。
【こちらもオススメ!】
合格体験記の一覧