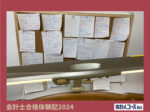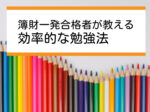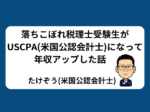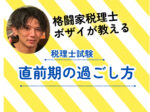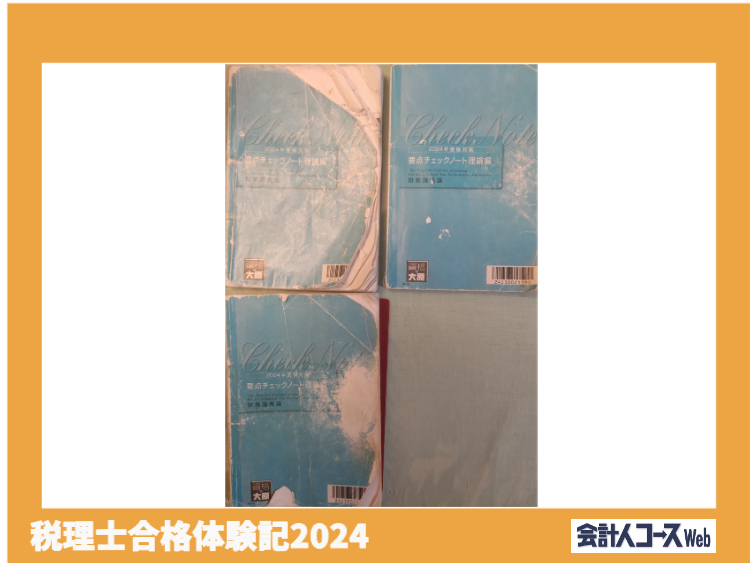
小栁 悠貴(30代 現在法政大4年)
<受験情報>
合格科目:簿記論、財務諸表論(令和6年度、初学)
学習スタイル:資格の大原(通学)
▶サムネイルは使い込んだ要点チェックノート(小栁さん提供)
税理士を目指したきっかけ
社会人として働く中で、確かな資格と技術を強みにしたいと考え、令和5年から簿記の勉強を始めました。
半年弱の独学で簿記2級に一発合格したことで、自分との相性の良さを感じ、9月から簿記論・財務諸表論の一発合格コースを受講することを決意しました。
教育訓練給付金制度を活用できたため、費用面の負担が少なかったことも大きな要因でした。
また、学習そのものが自分にとって苦ではなく、新しいことを覚えるのが楽しく、計算を解くことにやりがいを感じたことも決め手になりました。
通学を選択した理由は、当時の職種の関係上、仕事の拘束時間が長く、独学では学習の優先度を下げてしまう可能性があったためです。
明確に学習時間を確保するため、通学という選択をしました。
基礎期を耐え、環境を変える
9月から始まった年内学習期間、週4の基礎期は本当に忙しかったです。
ちょうど仕事の繁忙期と重なり、自宅に帰るのは週に3日ほど。
睡眠時間を確保するために会社に宿泊し、深夜の静かな時間帯に計算問題を解く生活を続けました。
宿題をこなすために平日の平均睡眠時間は4時間を切ることもありました。
しかし、その状態では総合問題に取り組む余裕はなく、睡眠不足の影響で理論の暗記も進みませんでした。
一日かけてもわずか3行しか覚えられず、翌朝には何も思い出せず愕然としたこともあります。
成績も振るわず、「このままではいけない、環境を変えなければ」と思いながらも、大原の授業には必ず通い続けました。
講師の先生方が「最後まで諦めずに通学する人にはチャンスがある」とおっしゃっており、その言葉を支えに学習を続けました。
この状況が変わったのは、会計事務所へ転職した冬頃。
年内最後の確認テストでは、成績は下位3割付近だったことを覚えています。
これらの苦しい状況が改善したのは、転職活動に成功してからでした。
転職先は繁忙期でも通学時間の確保を約束してくれる懐の深い会計事務所でした。
もちろん、通学日以外は残業や休日出勤がありましたが、以前と比べて圧倒的に勉強しやすい環境になりました。
また、業務で電卓を使う機会が増えたことで、計算処理の速度も向上しました。
転職後は、睡眠時間と勉強時間をしっかり確保できるようになり、1日の学習量が大幅に増えました。繁忙期以外は毎日総合問題を解き、余った時間で基礎テキストの復習を行い、寝る前と起床時には理論テキストの暗記をする習慣をつけました。
この学習習慣の安定化により、成績は徐々に向上。
4月には簿財ともに平均付近、6月には上位3割(ボーダーライン組)に入るかどうかのレベルまで到達しました。
定期試験の活用方法
定期試験はあくまでベンチマークであり、学習の定着を確認するための指標に過ぎません。
仮に試験時点で成績が振るわなくても、その時に出題された問題を解き直し、自分の中で理解できれば問題ないと思います。
ただ、そのベンチマークを活用し、時期や状況に応じて自分の立ち位置を意識しながら目標を設定すると、モチベーションの維持につながります。
私の場合、4月までに平均、6月までに上位3割に入ることを目標にしていました。
もし予想より成績が低く、目標との差が大きかった場合には、1科目に集中して勉強することも覚悟していました。
両科目とも安定ではありませんが、概ね目標範囲内には入れていたため、幸いにも同時合格を目指すことが出来ました。
また、直前の全国統一模試だけは特に重要です。
これは自分の立ち位置を確認する最後の試験となるため、その結果をもとに最終段階で何をすべきかが明確になります。
合格確実圏にいるなら現状維持で十分ですが、ボーダーラインを下回っている場合は基礎論点の見直しが必要になります。
私の場合は簿記論が上位19%、財務諸表論が上位43%でした。これまでの成績では常に財務諸表論の方が良く、上位30%付近を維持していましたが、公開統一模試の時だけは伸び悩んでいました。
ここで、私は実践形式の4時間試験の場合、後半は明らかに能力が落ちていると気づきました。
ケアレスミスが増え、計算スピードも落ちていたのです。
大原の講義や過去問では2時間の答練を解いても、その後の復習に長い時間を割いて次の答練までに十分なインターバルを取っていました。
この課題の洗い出しは、後から考えると、非常に重要な発見でした。
最終段階・試験準備
私は税理士試験を、「自分が出せる最高の点数を試験日に取りきる能力」が問われる試験だと考えました。
直前模試の結果から、私は二科目ともボーダーラインだと認識していました。
残された時間が限られている中で、多くの受験者に競り勝つ必要がありました。
そこで私は、体調面の調整について徹底的に考え、追及することにしました。
税理士試験は人間が受験します。
移動時間も考えれば半日は気が抜けず、受験者2万人の中には体調不良者も出ることが考えられます。
自分の体調を万全にするだけで、多くの他の受験者に対して抜きんでる可能性があると考えました。
これは統一公開模試を踏まえた経験があったために得られた結論でした。
そこで私は、まず税理士試験2週間前に試験会場の下見に行きました。
教室の広さや空調が効いている施設の範囲、最寄りのコンビニに電車の頻度など様々な要素を実際に見て考え、当日に試験を受ける上で必要な情報を可能な限り調べあげました。
まとまった休みを取れる1週間前からは毎日試験時間に合わせて過去問、答練問題を解きました。
昼食休憩時間中には終わった問題について考えず、財表の理論ノートや総復習をする練習を重ねました。
睡眠時間も完全に固定し、下剤などでトイレの時間も重ならないように調整しました。
3日前からは食事のメニューも完全に固定していました。
油の濃いものは避け、栄養素と必要カロリーも意識して厳密に決めていました。
私は昨年の試験において特別優れたものは持っていないと思います。
ただ、この最後の準備段階については誰よりも入念に準備したと自信をもって言えます。
少なくとも、その自信があることで当日の不安はほとんどありませんでした。
その結果、試験当日の答練を復元したところ簿財共にケアレスミスがゼロでした。過去の答練でも例はなく、20回に1度の結果を引き当てた感覚があります。
ただ、その20回に1度の結果を引き当てるための努力は、正しく出来ていたのではないでしょうか。
おわりに
税理士試験は社会人の立場からは非常に過酷な試験だと思います。
9月からの通学組は30名以上いたはずですが、年明けには半分に減っていました。最終講義に残っていた者は10名もいませんでした。
受験者の方々にはそれぞれの生活があり、一概に正解と言えるものはないと思います。
ただ、私の場合は必要と感じたならば環境を変えること、変えるのを恐れないこと、なによりも「絶対に合格する。税理士になる」という強い気持ちを持ち続けたことが、合格の決め手になったと考えています。
現在、私はより良い税理士となるべく大学に戻り、勉強を続けています。
税法初年度の挑戦となりますが、今年も集中して課題に取り組み、自己を改善し、来年も体験記を執筆できるよう精進していきたいと思います。