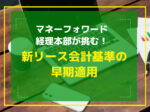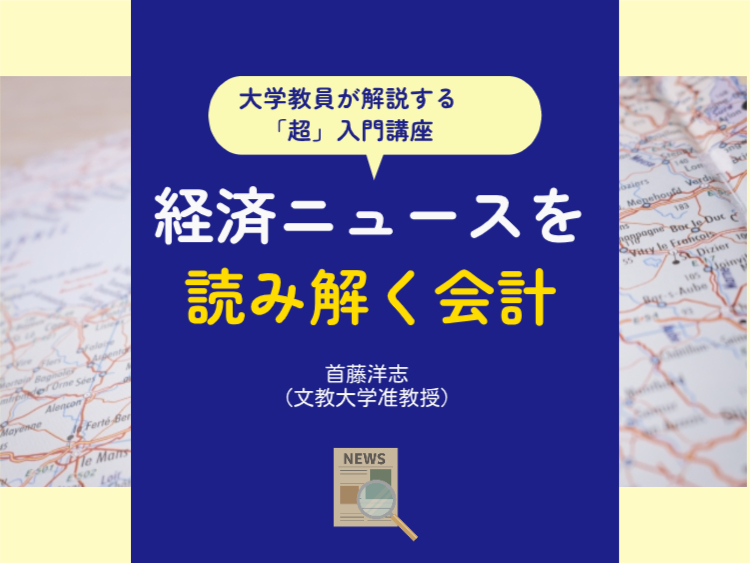
【編集部より】
話題になっている経済ニュースに関連する論点が、税理士試験・公認会計士試験などの国家試験で出題されることもあります。でも、受験勉強では会計の視点から経済ニュースを読み解く機会はなかなかありませんよね。
そこで、本企画では、新聞やテレビ等で取り上げられている最近の「経済ニュース」を、大学で教鞭を執る新進気鋭の学者に会計・財務の面から2回にわたり解説していただきます(執筆者はリレー形式・不定期連載)。会計が役立つことに改めて気づいたり、新しい発見があるかもしれません♪ ぜひ、肩の力を抜いて読んでください!
首藤洋志(文教大学経営学部・准教授)
こんにちは、文教大学の首藤洋志です!
会計関連の資格試験勉強に取り組む中、インターネットの記事を読んだりテレビの経済ニュースを見ていてイメージのしづらい、経済・社会的な専門用語に出会ったことはありませんか?
例えば、為替変動(円高・円安)、インフレ(率)、金利の上昇・下落、ベア、関税、サステナビリティ、ダイバーシティ、パーパス(経営)、ESG、CSR、ガバナンス、コンプライアンス、etc…挙げ始めるとキリがありませんね。
このような専門用語の中には、資格試験に直接的な関係を有するもののみならず、みなさんが将来選ぶ仕事に密接に関わっているものもあります。
コラムの全体像
今回のコラム(全2回)は、会計関連の資格試験勉強に取り組んでいるみなさんが、次の問いに答えるためのヒントになれば、との思いで執筆しました。
ちょっと難しい経済・社会的な専門用語をどう資格試験勉強と関連付け、どう向き合えば、未来志向の学びを深めていくことができるのか?
為替変動による身近な影響を想像する?
つい最近(2024年)まで、「歴史的な円安」、「1ドル=160円台」、などというニュースを耳にしていたことは記憶に新しいかもしれません。しかし、最近(2025年7月上旬のコラム執筆時点)、一転して、「円高、営業益2.2兆円下押し・・・為替、一点逆風に」(2025年7月2日、日本経済新聞朝刊)という新聞記事を目にしました。
この記事を簡単に要約すると、次のようになります。
2026年3月期の期末(2026年3月末)まで、今の為替相場(だいたい1ドル145円前後)が続いた場合、2025年3月期(前年度)の平均為替相場からの大幅な「円高」により、輸出による売上が大きい企業(例えば、輸出企業の代表格である自動車業界のトヨタ自動車など)は、減益影響がかなり大きくなる。
このように、為替相場が円高に向かうのか、円安に向かうのか、によって、日本企業の業績に大きな影響が出ることになります。財務諸表との関わりで言えば、為替差損益などが、わかりやすく変動します(収益⇔費用の転換を含みます)。極端な例だと、前期は数百億円の為替差益だったのに、当期は一転して数百億円の為替差損になったりするケースが生じるということです。事業規模によっては、利益に与える金額インパクトも相当なものとなります。
為替相場の変動による影響は、日本で普通に生活している私たちにも生じています。しかし、実際には、私たちに為替変動がどのような影響を及ぼしているのかについては、想像しづらいと思いませんか?
以下では、「資産形成(投資)」と「海外旅行」の事例を取り上げ、為替変動が日常生活の中で私たちに及ぼす影響を考えてみましょう。
資産形成(投資)
2024年に始まった新NISA(少額投資非課税制度)などの影響により、資産形成(投資)に興味を持ち始めた方もいるのではないでしょうか?
つみたてNISAを始めたことにより、一般企業の株価などに関心を持ち始めた方もいるかもしれません。
例えば、iPhoneでおなじみの、アップル社の株価は、1株あたりおよそ210ドル(2025年7月上旬現在)です。
これを同じタイミングの為替相場、1ドル145円で換算すると、あなたは30,450円でアップル社の株式を手にすることができます(手数料等は考慮していません)。
しかし、同じアップル社の株式(株価は今と同水準と仮定する)を1年前に1ドル160円で購入していたとしたら、同じ1株を手にするのに、33,600円が必要だった計算になります。
つまり、1年前にアップル社の株式を買って保有していたら、株価そのものに変動はなくても、為替変動によって、評価額が3,000円以上目減りしてしまうのです(=評価損)。
自分事として考えると、結構大きな影響があると思いませんか?
このように考えると、同様の影響が、企業の輸出・輸入取引や有価証券に対する投資取引などで起きていることは、想像しやすいでしょう。
無論、いわゆる資産形成(投資)に直接的な関係はないかもしれませんが、企業の業績は、商品やサービスの価格などにも影響を及ぼしうるので、いちステークホルダー(消費者)としても、為替の影響を間接的に受けている可能性はありますね。
海外旅行
夏休みなどの長期休みに、海外旅行を考えている方もいると思います。海外旅行においては、為替相場は重要な検討事項にあたりますね。
例えば、一見なんの変哲もないこのラーメン、いくらだったと思いますか?
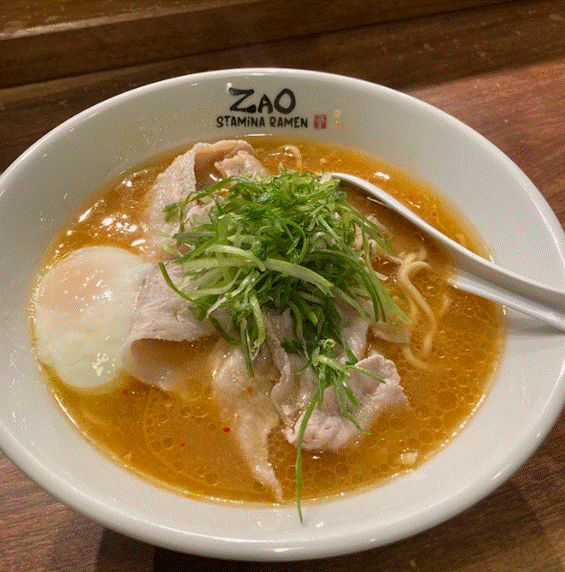
日本でこのラーメン(たしか、辛味噌味。豚肉と半熟卵とちょっとした野菜がのっていた)を食べたら、感覚的には800円くらいかな、という印象です。
しかし、2023年に、私が実際にこのラーメンをアメリカの首都Washington, D.C.(ワシントンD.C.)の近くのBethesda(ベセスダ)という街でいただいたときの支払額はなんと・・・
3,000円!!!
※値段の内訳:ラーメン自体の値段:約18ドル(税込み)、当時の為替レート:約152円、チップ:約300円
なんとなく、アメリカのラーメンは高価、という印象を持ちながらも、実際に食べてみないことには・・・と思い、お店に入ったが最後。
値段に驚き、お店に入ったことを若干後悔しながらも、お店を出るのも恥ずかしく、泣く泣く3,000円のラーメンをおいしくいただきました(もちろん、スープもありがたく飲み干しました・・・)。
余談ですが、最近は日本のラーメンも随分と高くなってきましたね・・・
私が大学生の頃、福岡の中心地でよく280円の博多ラーメンを食べたものです。これがインフレ?
インフレの体感?
ラーメンの値段が高い(もしくは、高くなってきた)というのは、インフレに関係する話でもありそうです。
前述の福岡で食べられていた280円ラーメンは、数年前に行ってみたら360円に値上がりしていました(それでもまだだいぶ安い!)。
わかりやすいのはマクドナルドです。
私が小学生の頃、マクドナルドのハンバーガーやチーズバーガーを、1個あたりそれぞれ65円、80円で食べることができていた事実は、忘れもしません。
おそらく、平日限定のキャンペーン時限定の価格であり、常時この価格、というわけではなかったと思いますが、今のハンバーガーの値段は、3倍近くになっていますね。
ちなみに、2025年4月に出張で訪問したスイスのフリブールという街で頂いた、マクドナルドの一番安いセット(普通のマックチキン+ポテトM+ソフトドリンクM)は、およそ2,100円でした…。「為替変動×インフレ」のダブルパンチは本当にきついです。

まとめ
会計情報に話を戻すと、有価証券報告書などの定性的な情報の中で、為替変動やインフレが取り上げられる機会は増えています。
会計や簿記で向き合う問題を、ただ目の前にある解くべき問題として捉えるのみでは、「学び」を私生活やキャリアに活かすという意味で、有意義さや面白みの程度を高めるのに不十分かもしれません。
たまには、興味のある上場企業の決算発表や財務情報(「決算短信」や「有価証券報告書」はHPで簡単にダウンロード可能)に目を向けてみたり、私生活で気づくお金関連の事象を会計的に捉えるなどして、日ごろ学んでいる会計の知識を実践的に活用してみることもおすすめです。
コラム第2回では、「サステナビリティ情報と会計・監査の意義」(財務会計と監査関連)、というテーマを取り扱いますので、ぜひ勉強の息抜きに読んでみてください!
<執筆者紹介>
首藤 洋志(しゅとう ひろし)

文教大学経営学部准教授。公認会計士。
九州大学経済学部卒、博士(経済学・名古屋大学)。
2011年~2020年:公認会計士として監査業務に従事。
2020年~:大学教育及び財務会計・監査研究。
<主な論文>
「サステナビリティとパーパス経営―人的資本を中心とした会計学研究からのアプローチ―」『経営教育研究』2025年, Vol.28, 51-61頁(単著)。
「大手監査法人のダイバーシティ実現と公認会計士の人事業績評価における課題」『国際会計研究学会年報』2024年度第1号, 31–58頁(共著)。
“Impact of Voluntary IFRS Adoption on Accounting Figures: Evidence from Japan” Accounting, Economics, and Law: A Convivium, 2023, pp. 1–55(共著).
著者情報の詳細は、こちらよりご覧ください!




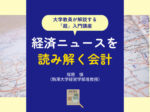
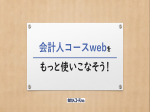







--150x112.jpg)