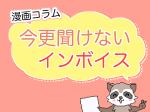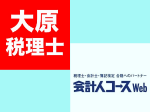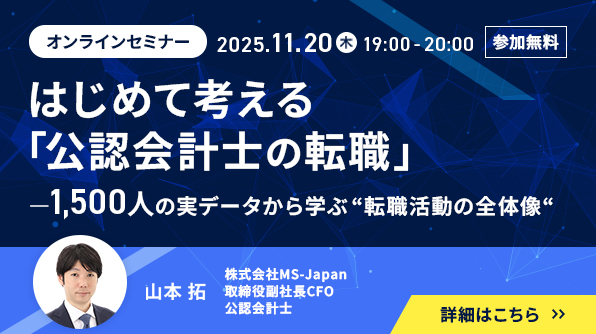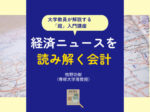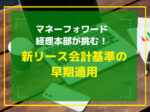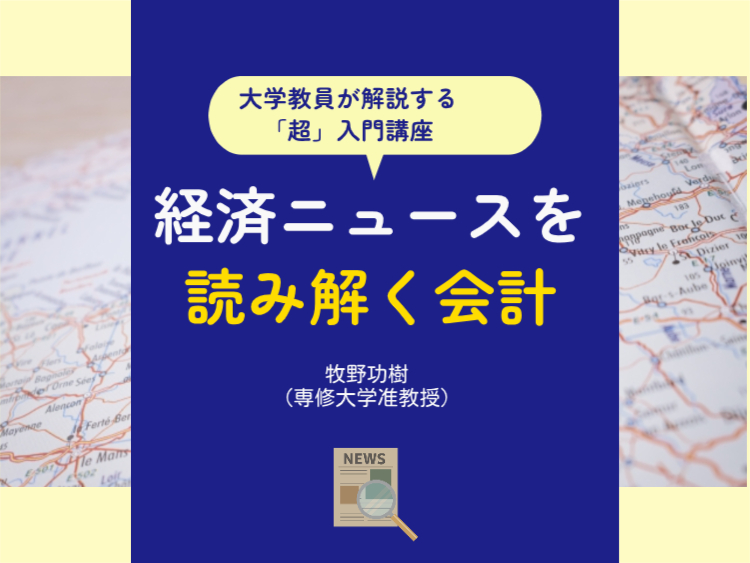
専修大学商学部・准教授 牧野功樹
【編集部より】
話題になっている経済ニュースに関連する論点が、税理士試験・公認会計士試験などの国家試験で出題されることもあります。でも、受験勉強では会計の視点から経済ニュースを読み解く機会はなかなかありませんよね。
そこで、本企画では、新聞やテレビ等で取り上げられている最近の「経済ニュース」を、大学で教鞭を執る新進気鋭の学者に会計・財務の面から2回にわたり解説していただきます(執筆者はリレー形式・不定期連載)。会計が役立つことに改めて気づいたり、新しい発見があるかもしれません♪ ぜひ、肩の力を抜いて読んでください!
前回のコラムでは、WBCという国際大会を取り上げました。かつて「人気のセ、実力のパ」といわれた日本のプロ野球も、今はかつてない盛り上がりを見せ、その構図は近年大きく変化しています。
観客層の広がりやデジタル技術の進展を背景に、パ・リーグ各球団が経営革新を進めています。その先頭に立つのが、北海道日本ハムファイターズです。2022年に就任した新庄剛志監督は、「優勝よりもファンを楽しませたい」と語りました。一見パフォーマンスのようですが、管理会計の観点からは、短期的な利益よりも長期的な顧客価値の最大化を志向する戦略的マネジメントの体現といえます。
その理念を具現化したのが、2023年開業の「エスコンフィールドHOKKAIDO」です(日本経済新聞2025年5月2日付「北海道のスタジアム、エスコンフィールドの際立つ集客力」参照)。同球場の運営には、戦略的コストマネジメント(Strategic Cost Management:SCM)、KPI(Key Performance Indicator)マネジメント、そしてデータ駆動型管理会計(Data-driven Management Accounting)という3つの中核概念が実装されています。
単なるコスト削減から戦略的コストマネジメントへ
SCMは単なるコスト削減ではなく、競争優位を支えるためにコスト構造を設計する枠組みです。SCMは、Shank and Govindarajan(1993)が体系化した概念であり、以下の3要素から構成されます。
(1)バリューチェーン分析(Value Chain Analysis)
企業活動を上流から下流までの価値連鎖としてとらえ、どこで付加価値を最大化すべきかを明確にします。エスコンでは、試合開催を核に、飲食・宿泊・観光を組み合わせた「地域体験型バリューチェーン」を形成し、球場そのものを「地域価値を創出する装置」として再定義しています。
(2)コストドライバー分析(Cost Driver Analysis)
コスト発生の要因を特定し、価値創造につながる活動に重点投資を行います。エスコンでは、照明演出や映像制作、ファンサービスなど、従来は削減対象とされがちな支出を「体験価値を高める戦略的支出」として積極的に管理しています。
(3)ライフサイクルコスト分析(Life-Cycle Costing)
建設から運営・維持管理までを包括的に捉えます。エスコンでは短期損益に依存せず、飲食・物販・イベントなどの複合収益構造を基盤に、長期キャッシュ・フローを最適化しています。このようにエスコンの経営は、コストを削減の対象ではなく、価値創造ドライバーとして再設計する戦略的コストマネジメントを具現化した好例です。
非財務指標による戦略モニタリング
エスコン開業にあわせ、ファイターズは非財務データを活用したKPIマネジメントを導入しました。球団資料(ファイターズ2023年度報告)などによれば、主要KPIは、①来場者の平均滞在時間、②1人当たり飲食・物販支出額、③SNSでのエンゲージメント率、④再来場率・ファンクラブ加入率です。
これらは、財務成果の前段階を測定する先行指標であり、戦略の実行プロセスを可視化する管理会計情報です。バランスト・スコアカード(Balanced Scorecard:BSC)の枠組みに基づき、「学習と成長」→「内部プロセス」→「顧客」→「財務」という因果連鎖に沿ってKPIを設計・管理しています。
たとえば、スタッフ教育やデジタル活用(学習と成長)の強化が、試合運営やイベント設計の改善(内部プロセス)を促します。その結果、来場者体験の質(顧客視点)を高め、最終的に収益の安定化(財務視点)につながります。KPIマネジメントは、こうした戦略的因果関係をモニタリングする管理会計システムであると同時に、戦略仮説を検証するデータでもあります。非財務データを分析し、次のイベント設計や価格施策に反映するなど、リアルタイムに戦略を修正する循環を築いています。
データ駆動型管理会計
エスコンでは、POSデータ、入場ゲート通過数、Wi-Fi接続履歴などの行動データをリアルタイムに集約・分析しています。これにより、従来の過去指標を報告するだけでなく、戦略とオペレーションを結ぶデータ駆動型マネジメント・システムに進化しています。
まず、試合日ごとの損益を即時に可視化し、「どの試合が、どの要因によって黒字/赤字となったのか」を分析し、販売施策や価格設定を当日中に修正できます。これは、伝統的な実績報告による事後管理から、リアルタイムな差異分析による先制的コントロールへの移行です。
また、ローリング・フォーキャストによる動的予算管理を導入し、販売・来場・天候などの変動データに応じて利益見通しを随時更新することにより、計画と実績の乖離を最小化し、資源の再分配を機動的に行っています。さらに、気象条件・試合カード別の来場実績と販売データを関連づけ、コストドライバーを特定しリソース配分を最適化しています。観客構成の変化に応じて在庫水準や人員配置を即時に調整し、過剰在庫や人件費を抑えつつ販売機会を最大化しています。これはSCMにおけるコスト構造設計の実践例であり、データ駆動型管理会計の典型です。
会計情報は過去の報告ではなく、未来の行動を設計し、戦略実行を指し示す情報として機能しています。戦略的コストマネジメントの視点から見れば、コストは削減の対象ではなく、戦略実現のために設計すべき構造です。
エスコンフィールドの事例は、データ駆動型管理会計がその思想を体現していることを示しています。
おわりに
エスコンフィールドの事例は、コストを戦略資源として再設計するSCM、KPIマネジメント、データ駆動型管理会計を統合した実践です。管理会計が財務成果を測る技法から、戦略を動かす組織的インフラへに進化していることを示しています。
新庄監督の「ファンを楽しませる」という言葉は、顧客価値を中心に据えた戦略の明確化であり、その実現を支えるのが、数字を戦略へと昇華させる管理会計の力です。
エスコンフィールドは、管理会計が戦略・組織データを統合し、未来の経営を設計する知識体系に進化していることを象徴する実践の場なのです。
【参考文献】
Shank, J. K., and Govindarajan, V. (1993). Strategic cost management: The new tool for competitive advantage. New York, NY: The Free Press.
牧野功樹(まきの・こうき)
大学卒業後は銀行へ就職し、企業経営の現場について学ぶ。その後、大学院修士課程を修了し、釧路の短期大学で講師をしながら大阪府立大学の博士後期課程へ進学し、博士(経済)を取得。拓殖大学商学部助教・准教授を経て、現在は専修大学商学部准教授。専門は中小企業の管理会計、資本予算。詳細はウェブページから参照が可能。