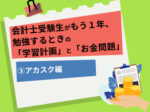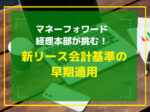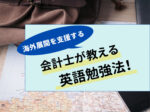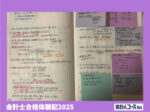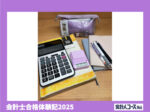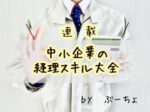投資銀行は財務数値をどう見るか?~第1回:投資銀行と財務数値の関係とは
- 2025/10/31
- コラム

藤波由剛(プリンシプルズ株式会社代表取締役CEO)
村橋秀一(公認会計士)
はじめに
皆さん、はじめまして。
プリンシプルズの藤波と申します。
前職は投資銀行でM&Aアドバイザリーなどを担当し、現在は経営やM&Aの現場で実践できる財務・バリュエーションの専門的なスキルを投資銀行や事業会社の経営企画部門などへトレーニングする仕事をしています。
今回、ご縁があって「投資銀行の視点で財務をどのように捉えられるか」をテーマに連載します。
宜しくお願いします。
なお、本連載では、一般の読者を想定し表現はわかりやすさを優先しています。
そのため、専門的には厳密でない表現を用いる場合があることをご了承下さい。
また、内容はすべて筆者の個人としての見解であり、いかなる組織の意見を代表するものでもありません。
投資銀行は証券会社の法人部門
第1回のテーマは「投資銀行と財務数値の関係」ですが、前提として投資銀行について簡単に紹介します。
紹介にあたって、まず直接金融と間接金融からお話しましょう。
企業が事業を進めるにあたってお金が足りない時、資金を調達することになりますが、その方法として、「直接金融」と「間接金融」の大きくふたつの方法があります。
「直接金融」はお金の出し手である法人・個人から企業が資金を直接調達するやり方、「間接金融」はお金の出し手である法人・個人と企業の間を「銀行」が仲介し、法人・個人が銀行へ預けたお金を企業が銀行から融資を受け借りるやり方です。
前者の直接金融で、お金の出し手を市場から広く募る場合、株式や債券などの「有価証券」を企業が発行して取引する形をとることになり、有価証券の取引は証券会社が扱います。
日本で投資銀行とは主に「直接金融を担う証券会社の法人部門」を意味すると思っていただくと良いでしょう。
投資銀行は株式も債券も扱いますが、株式の取り扱いが事業の大きな部分を占めます。
投資銀行の株式に関連する代表的なサービスとして、「株式の引き受け」と「M&Aアドバイザリー」があります。
株式の引き受けとは
「株式の引き受け」では、資金調達のために株式を発行する企業(業界では「発行体」と呼びます)に対する発行実務のサポートと、発行された株式の投資家への販売を行います。
例えば、ベンチャー企業が新しく上場することをIPO(新規株式公開)と呼び、よくニュースになりますが、証券会社から見るとIPOのサポートは株式引受業務の一種となります。
ちなみに、なぜ「引き受け」と呼ぶかと言うと、企業が株式を発行し市場を通じて広く多くの投資家に持ってもらいたい場合、「企業が発行した株式を証券会社が企業からいったん買い取って=引き取って、その株式を証券会社が改めて投資家へ販売する」という流れをとるからです。
M&Aアドバイザリーとは
「M&Aアドバイザリー」は、M&A(会社の買収・売却)を行いたい企業へ、M&Aに関連するアドバイスを提供するサービスです。
このようなサービスを提供する人は、「財務アドバイザー」または「FA(Financial Advisor)」とも呼ばれます。
アドバイスの範囲は非常に幅広く、例えば買収を行いたい企業が顧客であれば、以下のような論点を検討し顧客企業へ助言します。
・買収のターゲットとしてどのような会社が候補となり得るか
・候補となる会社にどのようにアプローチをするべきか
・候補となる会社(対象会社)の買収を行う上で、どのような取引手段(スキーム、ストラクチャー)をとるべきか、そのリスクや論点は何か
・対象会社の価値評価(バリュエーション)と買収価格をどう考えるか
・対象会社の株主との諸条件(買収価格、その他取引条件等)の交渉をどのようにすべきか
なお、これらには法務・会計・税務の議論が含まれますので、そのような論点は弁護士・会計士・税理士の先生と一緒に検討し顧客企業と議論していきます。
また、上記とは反対に、保有する企業の売却を行いたい顧客に対して売却に関する助言を行うこともあります。
企業は定性的な戦略の議論と定量的な財務の議論で経営の意思決定を行う
今度は企業の視点で考えてみましょう。
企業は株式発行やM&Aといったアクションの意思決定をどのように行うのでしょうか。
これらは経営レベルでの意思決定であり、経営者は「定性的」「定量的」な議論で判断を行います。
定性的な議論では、自社の戦略や目標に基づき、アクションが必要かどうかを判断しますが、今回のテーマではないのでこれ以上の説明は省略します。
定量的な議論では、「会社の数字」に基づき、アクションの必要性を判断します。
ここで、「会社の数字」とは、基本的に「財務数値」を意味します。
財務数値に基づき企業のファクトを見定める
そもそも財務数値とは何なのでしょうか?
会社は、社員の採用、取引先からの仕入、顧客への製品・サービスの販売などさまざまな企業活動を行いますが、ほぼすべての企業活動は「お金」のやり取りを伴います。
これらの「お金」のやり取りを、一定のルール(簿記・会計)にしたがってまとめたものが「財務数値」です。
著名な経営者である稲盛和夫氏(故人)は、「稲盛和夫の実学 経営と会計(日経ビジネス人文庫)」の中で、「会計の数字は飛行機の操縦席にあるコックピットのメーターの数値に匹敵するもの」であると述べています。
筆者はこの表現が好きでよく紹介するのですが、財務数値とは「企業活動を『数字』で表したもの」であり、財務数値に向き合うとは、数字を通じて会社で起きた様々な出来事=ファクト(事実)を理解することであると言えます。
財務数値に基づいて判断をするとは、会社のファクトを見定めて意思決定をすることなのです。
投資銀行は、財務数値の視点で顧客企業の意思決定をサポートします。
株式発行であれば、顧客企業の資金需要に対して顧客企業の事業計画や財務状況に照らしてどの程度の資金調達が必要か、M&Aであれば対象会社の買収価格としていくらまでであれば財務的に適切な投資と言えるかといったことを検討します。
投資銀行にとって、財務数値とは、顧客企業や対象会社の「ファクト」を見定め、顧客企業や関係者と経営の議論をするために必要不可欠なツールであると言えます。
投資銀行のもうひとつの顧客は「投資家」
ここで、投資銀行には株式や債券の売買を希望する顧客とは別の顧客・取引先が存在します。
それは投資家です(厳密には、証券会社において投資家と直接取引を行うのは投資銀行部門ではない別の部門なのですが、ここでは表現を単純化しておきます)。
例えば、株式の発行(増資)であれば投資家に株式を購入してもらう必要がありますが、投資家に「この増資は株式を発行する企業の企業価値向上につながるものだ」と納得してもらう必要があります(そうでなければ投資家は株式を購入してくれません)。
別の例で、例えばある上場会社が別の企業を買収する際、(この場合は投資銀行の直接の取引先ではありませんが)買い手企業の株主や市場の投資家(買い手企業の株式に投資するかもしれない買い手企業の潜在的な将来の株主)に「この買収は買い手企業の企業価値向上につながる取引だ」と納得してもらう必要があります(そうしなければ買い手企業の株価が下落してしまいます)。
このように、投資銀行は投資家ともコミュニケーションをとれる必要があるのです。
投資家は財務数値で企業を見て、儲けの数字で投資判断を行う
では、投資家はどのように投資判断をするのでしょうか?
これは非常に単純で、投資家は「儲かるか」で判断します。
そして、投資家は儲かるかを「数字」で判断します。例えば、A社の株式を500円で購入する投資家は「この株式はいずれ 700円で売れるはずだから」と考えて株式と購入するわけです。
では、どのように投資家は「A社の株式は700円になるはずだ」と判断するのでしょうか?
投資にはいくつかの手法がありますが、企業の業績を重視して投資判断を行う場合、投資家は経営者と同じように企業の戦略と財務数値を検討し投資判断を行います。
このように投資判断を行う投資家をファンダメンタル投資家と呼び、プロのファンダメンタル投資家は必ず財務数値を見ます。
投資銀行は、このような投資家とも財務数値の視点で事業を語りコミュニケーションできる必要があります。
投資銀行は財務数値を触媒に企業と投資家を仲介する
以上をやや粗くまとめると、投資銀行は「財務数値」を触媒に、企業と投資家を仲介する仕事をしていると言えます。
ここまで読んでいただくと、投資銀行の仕事において財務数値を扱えることがいかに重要か理解いただけるのではないでしょうか。
それでは、投資銀行では財務数値を読む際にどのような視点を持っているのでしょうか。
この点を次回はご紹介したいと思います。
【プロフィール】
藤波由剛(ふじなみ・ゆうごう)
株式会社ワークスアプリケーションズでの法人営業担当を経て、野村證券株式会社にてM&Aアドバイザリーに携わる。2016年にプリンシプルズ株式会社を創業。投資銀行や事業会社の経営企画部門などの法人顧客へ「実務ができるようになる」研修と「実務力を測定する」評価を「BizObi(ビズオビ)」サービスとして提供。財務・バリュエーション領域ではコンテンツ制作・講師を担当。シカゴ大学経営大学院修了(MBA)。東京大学法学部卒業(学士)。私立開成高等学校卒業。共訳『人事と組織の経済学・実践編』(日本経済新聞出版社・2017年)。
村橋秀一(むらはし・ひでかず)
公認会計士。監査法人トーマツおよび東光有限責任監査法人で会計監査、フロンティア・マネジメント株式会社でM&Aアドバイザリー、優先株・ストックオプション評価を含む価値評価や財務DD、野村證券株式会社でM&Aアドバイザリーに携わる。2017年に村橋公認会計士事務所を設立。プリンシプルズ株式会社では、財務・価値評価領域のコンテンツ制作・講師を担当。東京大学大学院経済学研究科金融システム専攻金融工学専門修了(修士)。立命館大学経済学部卒業(学士)。日本公認会計士協会東京会広報委員会副委員長(現任)、日本簿記学会簿記実務研究部会委員(2023・24年)など。