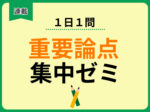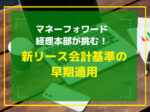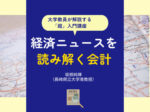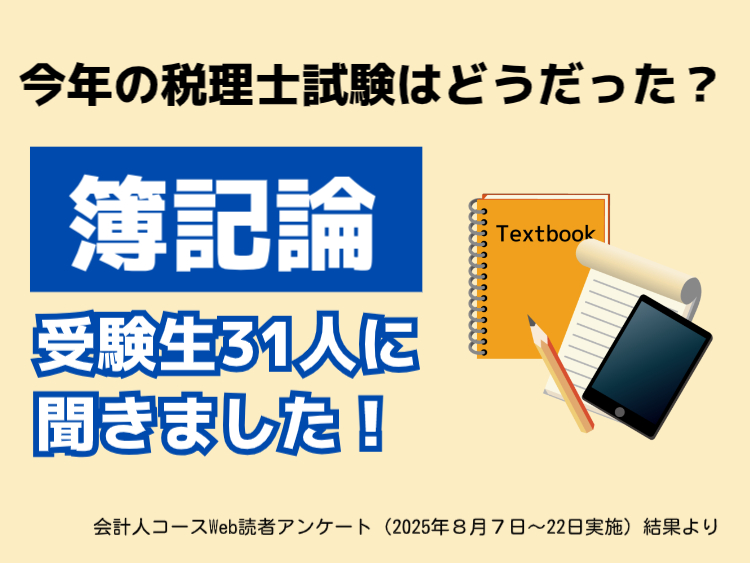
8月5日〜7日に令和7年度税理士試験が実施されました。すでに会計人コースWebでも簿記論に関する講評記事を公開しています。
また、国税庁ホームページでは、税理士試験(全科目)の試験問題・答案用紙に加え、「令和7年度(第75回)税理士試験出題のポイント」が公表されています。この「出題のポイント」は本試験に関する貴重な情報なので、今後、受験予定の方もしっかり目を通しておくことをオススメします。
とはいえ、特にはじめての場合では、どういったポイントを押さえるとよいかが掴みにくいもの。そんな時は、「かえる先生に聞く! 税理士試験「出題のポイント」から何がわかる⁉︎」をぜひ参考にしてください。
早いもので9月中旬となり、次年度の受験に向けて学習を始めた人も多いのではないでしょうか。
そんな今、「会計人コースWeb」が今年の税理士試験直後から実施した読者アンケートをもとに、簿記論・財務諸表論・税法科目にカテゴライズして、受験生のリアルな声をお届けします!(随時掲載予定)
なお、複数科目を受験した方の回答については、該当科目の内容をピックアップしてまとめています。
今年受験された人はもちろん、来年の税理士試験を受験予定の人も、ぜひ参考にしてください!
今年は何回目の簿記論受験?
今回の読者アンケートでは、簿記論を受験した31名の方に回答をいただきました。
まずは「今年の簿記論受験が何回目か」をお聞きしたところ、初受験の人よりも再受験の人が若干多い結果になりました。
(会計人コースWeb読者アンケート(2025年8月8日〜22日実施)結果から編集部作成)
本試験の「感想」や「手応え」はどうだった?
簿記論の本試験について、受験直後の感想や手応えをお聞きししました。手応えを感じた方も多かった一方、第3問の出題形式で戸惑った意見もありました。
・普段あまり見ない形式の問題に戸惑いました。(紫紺)
・まずまずの出来かと。(にゃん)
・例年より簡単に感じた。(こー)
・ボリュームはあるけど、各論点は簡単だった。(まゆごん)
・第1問、第2問は手応えがあったが、第3問がかなり難しく、解ける場所だけ拾う形になった。(とっちー)
・第3問が全く時間が足りず手応えはなかったです。(りん)
・ストックオプションの問題を4年度のところは計算で出ましたが、5年度のところが出ず、解答欄に何も記入せず、第3問に入りました。第3問を解いているときに試験時間が終了し、ストックオプションの計算のところが空白であることに気づき、しかも4年度の数値を入れるだけで良かったのに入れず、6点失点してしまった。後悔しています。 (つかの間のヒラメ)
・総合問題が面白かった。第1問を最後に回して時間が足りなくなってしまったのが残念。第2問を最後にするべきだったかも知れないが、ストックオプションは皆が得意な論点なのでやらないわけにはいかないと判断してしまった。(とな)
・第3問は出題形式に戸惑い、時間に追われたことも含め冷静になればできそうな問題もミスが多かった。(スマイリー)
・第3問の形式に面を食らいましたが、第1問と第2問は比較的迷うことなく解けました。終わった時の手応えはあまりありませんでしたが、自己採点では70点を超えて合格ボーダーを突破していました。(たろう)
・第1問は第2問はそこそこ解けていると感じ第3問に入って面食らってしまってしまいました。(さく)
「解けた問題」と「難しかった問題」はどれ?
簿記論の本試験について、どの問題が解けたか、難しかったかをお聞きしました。昨年のアンケートでは、「第1問が難しかった」という意見が目立ちましたが、今年は「第3問が難しかった」という意見が圧倒的でした。
・第3問の総合問題は何を聞かれているかを理解するのに時間がかかりすぎてしまいました。(kei.m)
・第3問の総合問題が全般的に難しかった。(にゃん)
・第1問、第2問は解けたが、第3問のリースの貸手、商品、売買契約が難しかった。(とっちー)
・第1問は転換社債型新株予約権付社債と有価証券期末処理以外の推定は解けました。転換社債については後TBの新株予約権から推定しなければならなかったことが、焦りから気付くことができませんでした。有価証券はいつもの図表を作り数値を当てはめしていくところまではやっていたのですが、取得時のレートをブランクにした推定の経験がなかったため、平均レートから償却原価を求める際に焦りが出て電卓ミスをしてしまいました。第2問はストックオプションで退職見込みゼロの年度は実退職者数で計算することを忘れており、ゼロとして計算してしまうミスをしてしまいました。第3問は答練で繰り返し出ていた典型パターンに頭が洗脳された状態で受けたため、まさかCFの推定簿記とは最後まで気付かずに試験を終了してしまいました。よって典型パターンで解ける箇所はなんとか押さえられたと思いますが、勘定分析の上算出しないと正解できない部分は全て落とす結果となりました。柔軟に現場対応をしないといけないとは、試験直前まで思ってはいたのですが、いざ始まり出して周りの電卓の打刻音がなり出したあたりから焦りが一気に出た気がしました。(モモンガ)
・解けた問題は、簿記論の事業分離の問題、財務諸表論の総合計算問題です。難しかった問題は、簿記論の総合計算問題、財務諸表論の引当処理の定義のところです。(つかの間のヒラメ)
・第2問が初見では難しかった。第3問は皆が言っているほど難しくなく、個人的には普通〜簡単のレベルだった。(やまちゅー)
・第3問が難しかったです。各予備校の解説動画では、実は前期及び当期末残高があるので、そんなに難しいものではないということでしたが、試験中にそこまで気がつく余裕はなかったです。第1問はほとんど解くことができました。第2問の問1は見た目は難しそうでしたが、8割くらいはあっていました。問2は基本的なところは解けましたが、一部予備校の模試で出ていたにも関わらず解けませんでした。(たろう)
*
簿記論の本試験に関するアンケート結果は参考になりましたか。
これから受験勉強を始める人は、ここから何かヒントを見つけていただけると嬉しいです!
――読者アンケートにご協力いただいた皆さま、本試験直後のお疲れのところにも関わらず、誠にありがとうございました!!