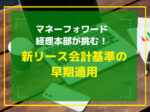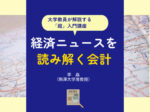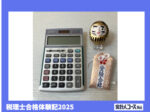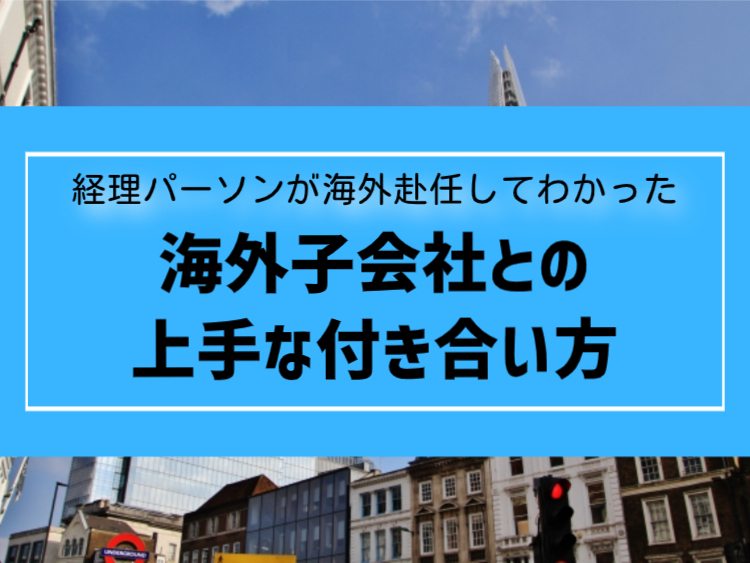
松岡俊(株式会社マネーフォワード執行役員グループCAO)
【編集部より】
国際的に活躍したいと思う経理パーソン向けに、海外子会社との上手な付き合い方について解説していただきます。
第1回:イントロダクション
第2回:日本と海外の経理実務差異~「ジョブ型」
第3回:日本と海外の経理実務差異~残業・有休(7月7日(月)配信予定)
第4回:日本と海外の経理実務差異~コミュニケーション(7月9日(水)配信予定)
第5回:まとめ~異文化理解を深め、グローバルな協業を円滑に(7月14日(月)配信予定)
英国赴任中に特に強く感じた具体的な「差異」
前回は海外での経理業務経験の中から、日本との「共通点」についてお話しさせていただきました。簿記や表計算ソフトといった普遍的なスキル、そしてコミュニケーション能力の重要性は、国境を越えて変わらないことを実感しました。
しかしながら、海外で働く中で、日本の常識が必ずしも通用しない「差異」に直面し、戸惑うことも少なくありませんでした。
これらの違いを理解し、受け入れることが、現地での業務を円滑に進める上で非常に重要だと痛感しました。
ここからは、私が英国赴任中に特に強く感じた具体的な「差異」について、自身の経験を交えながらご紹介していきたいと思います。
西洋鎧を着てご満悦の筆者
ジョブディスクリプション(職務記述書)の存在と役割
欧米ではジョブディスクリプションに各自の職務内容が詳細に記載され、基本的にはそこに記載された業務を遂行することになります。
日本のように自身の業務範囲外であっても、手が空いたからといって他のメンバーの業務を積極的に手伝うといったことは一般的ではなく、自らの担当業務が終わって定時になれば速やかに帰宅するというスタイルが見られました。
先述の通り、私は赴任直後、できるだけ仕事の幅を広げようと、私の本来の役割である本社へのレポーティング業務に関連して見受けられる課題などについて、プロセスにどのような問題があるのか確認して改善提案を行いました。
しかし、こうした動きは、当時の担当者からは必ずしも好意的に受け止められなかったように感じます。
私の行動は、彼らにとっては自分たちの責任範囲への「介入」と映ったのかもしれません。
今にして思えば、彼らの責任範囲をより尊重したコミュニケーションが必要だったと反省しています。
ジョブローテーションに対する考え方
上記とも関連しますが、ジョブローテーションについても考え方に大きな差異を感じました。
日本では、企業規模にもよりますが、経理部門内部でもローテーションで複数の業務を経験することが多いと思います。
私自身、1998年の入社以来、部門担当経理、原価計算・分析、固定資産、税務・単体開示、システムプロジェクト、連結と、ローテーションを通じて幅広く経験を積ませていただきました。
海外赴任後、3年後にはRtR(Record-to-Report)と言われる組織の責任者となり、部員も当初の2名から約13名に増加しました。
その際、私が過去に経験したように、メンバーにも業務の幅を広げてもらおうと、ジョブローテーションを提案したことがあります。
なお、私の赴任先では以下のような組織体系になっていました。海外赴任前には耳にしたことがありませんでしたが、このような区分は欧米では一般的とのことです。
- PtP (Procure-to-Pay): 購買申請から支払いまでの、サプライヤーとの取引に関わる一連のプロセス(購買、請求書処理、支払いなど)を管轄します。
- OtC (Order-to-Cash): 顧客からの受注から代金回収までの、顧客との取引に関わる一連のプロセス(受注、出荷、請求、売掛金管理、入金処理など)を管轄します。
- RtR (Record-to-Report): 日々の取引の記録から財務諸表の作成、報告までの、会社の財務状態を記録・報告するプロセス(仕訳入力、勘定調整、固定資産管理、決算報告など)を管轄します。
私が試みたのはRtR内部でのローテーションでしたが、そこでは想像以上の抵抗がありました。
メンバーからは、「このような変更は重大であり、ジョブディスクリプションも変更する必要がある」「業務効率が大幅に低下するのではないか」といった不安の声が上がりました。
その件については、一定の手続きを踏んで実行し、結果的にはメンバーから「仕事の幅が広がった」と感謝されましたが、これは日本的なやり方の押し付けだったかもしれないと内省し、同様のローテーションはそれ以降実施しませんでした。
周囲を見渡しても、VAT担当として30年、OtC担当として20年といったように、キャリアを通じて特定の領域を専門的に担当している方が多く在籍していました。
この点は日本の感覚からすると異質に感じるかもしれませんが、多くのメリットも存在します。特定の領域を長年担当することで専門性が高まり、深い業務知識と経験に基づいて、より効率的かつ正確に業務を処理できるという点です。
人間は「これはどのように処理するのだろうか」と考えることに最も多くの時間を費やすものです。私自身もローテーションの度に一から学び直し、多くの残業をしていた記憶があり、それはそれで成長の上では価値があったと思いますが、残業時間を減らすという意味では、英国のスタイルの方が効率的であったことは間違いないでしょう。
これにはそれぞれメリット・デメリットがあり、どちらが優れているという問題ではないと思います。ただ、日本企業として海外グループ会社の経理部門と協業する際には、このような違いがあることを念頭に置いた方が良いかもしれません。
マネージャーの役割 – プレイングマネージャーは少数派?
次に、これもジョブ型雇用に起因する差異かと思いますが、マネージャーの役割の違いも顕著でした。日本では、特に経理のような専門職部門では、マネージャー自身も実務をこなしながらチームをマネジメントする「プレイングマネージャー」も少なくないのではないでしょうか。
しかし、英国の職場では、マネージャーは基本的にマネジメント業務という「ジョブ」に専念し、部下の育成や業務進捗の管理、部門間の調整といった役割に重きを置いているように感じました。
もちろん、必要に応じて実務のサポートに入ることもありますが、日常的にプレイヤーとして最前線に立つことは少ない印象です。そもそもジョブローテーションで様々な担当を経験してきたわけではないため、細かい業務については必ずしも熟知していない、ということもあるのかもしれません。
赴任時の英国人上司も、まさに「プロフェッショナルマネージャー」という印象でした。
オペレーションの詳細を熟知していてそれを前提に実務上のアドバイスをするというよりは、明確な目標設定、傾聴力、動機づけ、コミュニケーションなど、マネジメントスキルが非常に優れており、その方からマネジメントについて多くのことを学びました。
私は海外赴任して初めて2名の部下(ナイジェリア人、リトアニア人)ができました。
そのため、マネジメントとは何かという基礎ができておらず、自分が実務をこなす姿を見せることで理解してもらえれば良いだろう、程度に考えていました。
しかし、その上司との出会いが、マネジメント業務やソフトスキルの重要性について私の意識を大きく変えるきっかけとなりました。
第3回以降も、その他に感じた差異について深堀りしていきたいと思います。
【著者プロフィール】
松岡俊(まつおか・しゅん)
株式会社マネーフォワード
執行役員 グループCAO
1998 年ソニー株式会社入社。各種会計業務に従事し、決算早期化、基幹システム、新会計基準対応 PJ 等に携わる。英国において約 5 年間にわたる海外勤務経験をもつ。2019 年 4 月より株式会社マネーフォワードに参画。『マネーフォワード クラウド』を活用した「月次決算早期化プロジェクト」を立ち上げや、コロナ禍の「完全リモートワークでの決算」など、各種業務改善を実行。中小企業診断士、税理士、ITストラテジスト及び公認会計士試験 (2020 年登録)に合格。