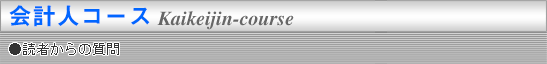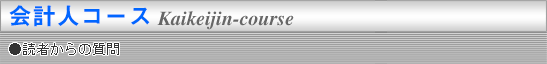|
崋丂丂悢
|
棑丒暸丒崁栚
|
幙丂丂栤
|
夞丂丂摎
|
|
2014擭1寧椪帪憹姧崋乽寁嶼椡僗僺乕僪僠僃僢僋乹幮嵚乺乿
|
p.52丂夝愢丂塃抜丂壓偐傜5峴栚
幮嵚敪峴旓偺彏媝偵偮偄偰
|
乽亊2擭10寧1擔乮攦擖彏娨偟偨偲偒乯乿偺②乮僴乯偺幮嵚敪峴旓徚媝暘偺寁嶼曽朄偵偮偄偰嫵偊偰偔偩偝偄丅
枹宱夁寧悢暘21寧傪徚媝偡傞揰偼棟夝偱偒傞偺偱偡偑丄亊2擭4寧1擔偐傜摨擭9寧枛暘偺幮嵚敪峴旓偺彏媝偑峴傢傟偰偄側偄偺偼側偤偱偟傚偆偐丅
|
幮嵚敪峴旓偺彏媝偼丆偛巜揈偺偲偍傝丆幮嵚偑攦擖彏娨偝傟傞偐丆斲偐偵偐偐傢傜偢丆帪偑宱夁偟偨晹暘偵懳墳偡傞嬥妟偼彏媝偟側偗傟偽側傝傑偣傫丅
偨偩丄崱夞偺栤戣偼屄暿偺巇栿栤戣偱丆彏娨偺巇栿偩偗傪偟偰傕傜偆堄恾偱弌戣偟傑偟偨丅
偦偺偨傔丆彏娨懝塿偺巇栿偵捈愙娭學偺側偄彏媝旓偺巇栿偼徣棯偝偣偰偄偨偩偄偨偺偱丆摨崋p.51偺傛偆側仏乽側偍丄彏娨帪傑偱偺幮嵚敪峴旓彏媝偺巇栿偼晄梫乿傪晅偟傑偟偨丅
杮帋尡偱偼丆屄暿偺巇栿偺栤戣偑弌戣偝傟傞壜擻惈偼掅偄偱偟傚偆丅
寛嶼帪偵偍偗傞嵿柋彅昞嶌惉偺帇揰偐傜栤戣傪撉傓偲偄偆丆偛幙栤幰偺巔惃偼朷傑偟偄偙偲偲巚偄傑偡丅偤傂偙傟偐傜傕懕偗偰偔偩偝偄丅
|
|
2014擭1寧椪帪憹姧崋乽寁嶼椡僗僺乕僪僠僃僢僋乹弮帒嶻夛寁乺乿
|
p.59丂夝愢乮俀乯丒夝摎乮俀乯帺屓姅幃偺庤悢椏偵偮偄偰
|
p.59乮俀乯偵偍偄偰丄張暘偵梫偟偨庤悢椏偼晅悘旓梡偲偟偰丄塩嬈奜旓梡偲偡傞巪偺愢柧偑偁傝丄夝摎棑乮俀乯偱偼巟暐庤悢椏3,000偑婰嵹偝傟偰偄傑偡丅懠偺嶲峫彂傪尒偨偲偙傠丄帺屓姅幃偺張暘偵學傞晅悘旓梡偼丄尨懃偲偟偰丄巟弌帪偵姅幃岎晅旓偲偟偰旓梡張棟偡傞偲偺愢柧傕偁傝傑偟偨丅姩掕壢栚偲偟偰丄巟暐庤悢椏偲姅幃岎晅旓偺偄偢傟偑揔愗側偺偱偟傚偆偐丅
|
|
|
2014擭1寧椪帪憹姧崋乽寁嶼椡僗僺乕僪僠僃僢僋乹堦斒彜昳攧攦乺乿
|
p.97屄暿栤戣曇1(忋偐傜11峴栚)丄p.98夝愢(嵍抜忋偐傜7丄10峴栚)
抣擖棪偵偮偄偰
|
巇栿栤戣曇偺堦斒彜昳攧攦偺屄暿栤戣侾乮倫.97丄98乯偵抣擖棪偲偄偆尵梩偑弌偰偒傑偡丅夝愢偱偼丄彜昳斕攧塿亐抣擖棪亖尨壙偲側偭偰偄傑偡偺偱丄棙塿壛嶼棪乮尨壙傪侾偲偟偨応崌偺棙塿偺壛嶼妱崌乯偲摨偠堄枴偱巊傢傟偰偄傞偺偱偟傚偆偐丅
|
幙栤撪梕偺偲偍傝丆抣擖棪偼棙塿壛嶼棪偲摨偠堄枴偱巊梡偟偰偄傑偡丅
|
|
2014擭1寧椪帪憹姧崋乽寁嶼椡僗僺乕僪僠僃僢僋乹奜壿寶庢堷乺乿
|
p.128丆129丂屄暿栤戣俀乮壓偐傜4峴栚乯
奜壿寶偺桳壙徹寯棙懅偵偮偄偰
|
奜壿寶庢堷偺屄暿栤戣俀偦偺懠桳壙徹寯乽H幮幮嵚乿偵偮偄偰幙栤偱偡丅
夝愢傪傒傞偲丄188愮僪儖乮帪壙乯偲180愮僪儖乮庢摼尨壙乯偲偺嵎妟俉愮僪儖乮亊CR乯傪偦偺懠桳壙徹寯昡壙嵎妟嬥偲偟偰偄傑偡偑丄彏媝尨壙朄傪揔梡偟偰媮傔偨係愮僪儖暘乮亊AR乯偺桳壙徹寯棙懅傪寁忋偟側偔偰傛傠偟偄偺偱偟傚偆偐丅
傑偨寁忋偟側偄棟桼偼丄帒椏偺乽拲係乿偵彏媝尨壙朄傪揔梡偡傞偲偄偆婰嵹偑側偄偺偱杮栤偺応崌寁忋偟側偄偺偐丄奜寶庢堷摍夛寁張棟婎弨拲10傪揔梡偡傞偲偒偵偼忢偵桳壙徹寯棙懅傪寁忋偟側偄偺偐偳偪傜偱偟傚偆偐丅
|
|
|
2014擭侾寧崋晅榐乽曤丒嵿丂幚慔僒僽僲乕僩Part1乿
|
p. 10丂妋擣栤戣4乮2乯
嬧峴懁偺枹庢棫偰偵偮偄偰
|
乮2乯偺枹庢棫妟300偼嬧峴懁偱偺憹壛偩偲巚偭偨偺偱偡偑丄側偤尭彮偵側傞偺偱偟傚偆偐丅
|
巇擖愭偵怳傝弌偟偨偲偒丄摉幮偱偼乮戄曽乯摉嵗梐嬥偲巇栿偟偰偄傑偡丅偙傟偼丄惓偟偄巇栿偱偡丅
偟偐偟丄巇擖愭偑枹庢棫乮嬧峴懁偐傜傒偰枹庢晅乯偱偁傞偨傔丄嬧峴偺巆崅偑懡偔婰挔偝傟偰偄傑偡丅傛偭偰丄儅僀僫僗偟傑偡丅
|
|
2014擭侾寧崋乽曤婰丂庛揰敪尒仺崕暈嫵幒乿
|
①倫.21偺栤戣搳帒桳壙徹寯偺昞帵壢栚偵偮偄偰丂
|
①搳帒桳壙徹寯偵娭楢夛幮姅幃偑偁傝傑偡偑丄夝摎偵摉偨偭偰偼偙偺暘傪搳帒桳壙徹寯姩掕偐傜丄娭學夛幮姅幃姩掕偵怳傝懼偊傞昁梫偑偁傞偺偱偼側偄偱偟傚偆偐丅
|
①偵娭偟偰丆娭學夛幮姅幃偲偟偰昞帵偡傞偺偑堦斒揑偱偡偑丆夛寁挔曤忋偼廬棃偐傜偺張棟傪摜廝偟偰搳帒桳壙徹寯偲偟偰張棟偡傞偙偲傕偁傝傑偡丅摎埬梡巻偐傜丆娭學夛幮姅幃偑側偄偺偱丆搳帒桳壙徹寯偵娷傔偰昞帵偡傞偲夝庍偟傑偡丅
|
②p.28塃抜丂2 B幮姅幃乮3乯偺夝摎
偦偺懠帒杮忚梋嬥偺攝摉偵偮偄偰
|
②B幮姅幃乮3乯偺夝摎
攧攦栚揑桳壙徹寯偱偦偺懠偺帒杮忚梋嬥偺攝摉傪庴偗庢偭偨応崌丄庴庢攝摉嬥偱巇栿偡傞偙偲偲側偭偰偄傑偡偑丄桳壙徹寯塣梡懝塿偲偟偰偄傞偺偼側偤偱偟傚偆偐丅
|
②偵娭偟偰丆攧攦栚揑桳壙徹寯偐傜惗偠傞攧媝懝塿丆昡壙懝塿偍傛傃攝摉嬥偵偮偄偰丆偡傋偰桳壙徹寯塣梡懝塿偲偟偰昞帵偡傞偙偲傕擣傔傜傟偰偄傑偡乮嬥梈彜昳夛寁偵娭偡傞Q仌A丂Q69乯丅
|
|
2013擭12寧崋乽僴僀僷乕丒僩儗乕僯儞僌PLUS曤婰榑乿
|
p.99丂椺戣侾偺夝愢偵偮偄偰
|
①亙昞俀丂棙懅朄偺僗働僕儏乕儖亜偱乽仏丂戄庤傕庁庤偲摨條偵丄強桳尃堏揮奜僼傽僀僫儞僗丒儕乕僗庢堷偱偁傞偙偲傪敾掕偟偨偺偪丄儕乕僗暔審偺峸擖壙妟乮54,300愮墌乯偐傜戄庤偺寁嶼棙棪偑3.42亾偱偁傞偙偲傪媮傔傑偡丅乿偲偁傝傑偡偑丄寁嶼棙巕棪3.42%偼偳偺傛偆偵媮傔傞偺偱偟傚偆偐丅
|
①戄偟庤偺寁嶼棙巕棪傪倰偲偡傞偲丄
12,000愮墌乛乮1亄倰乯亄12,000愮墌乛乮1亄倰乯2亄12,000愮墌乛乮1亄倰乯3亄12,000愮墌乛乮1亄倰乯4亄12,000愮墌乛乮1亄倰乯5亖54,300愮墌
丂偙傟傪夝偔偲丄倰佮0.0342乮亖3.42亾乯偲側傝傑偡丅
|
|
②媮傔傜傟偨応崌丄惂尷帪娫乮15暘乯埲撪偵夝摎偑壜擻偱偟傚偆偐丅
|
②偙偺栤戣偼丄夛寁巑抁摎幃偐傜偺弌戣偱偁傝丄媮傔傞寁嶼棙巕棪傪r偲抲偗偽丄偡傋偰傪15暘埲撪偱夞摎偡傞偙偲偼壜擻偱偡丅夝愢偺晹暘傪偛棗偔偩偝偄丅夝偔億僀儞僩偑傢偐傟偽夝偒捈偟偱丄15暘偱惓夝傪弌偡偙偲偼偱偒傞寁嶼検偱偡丅
丂偨偩幚嵺偺惻棟巑帋尡偺弌戣傪峫偊傟偽丄偙偺傛偆偵曽掱幃側偳傪梡偄偰丄棙棪傪媮傔傞栤戣偑弌傞壜擻惈偼旕忢偵彮側偄偲巚偄傑偡丅偟偐偟丄偨偲偊偽屌掕帒嶻偺庢摼尨壙傪X側偳偲抲偄偰丄捈愙朄偺挔曤壙妟側偳偐傜庢摼尨壙傪媮傔傞偙偲偼傛偔偁傞偙偲偱偡偺偱丄堦掕偺悢妛揑抦幆偼昁梫偲巚傢傟傑偡丅
丂崱夞愝栤俀偵偮偄偰偼丄侾乮侾乯丄俀乮侾乯丄俁乮侾乯埲奜偑夝偗偰偄傟偽廫暘崌奿揰偩偲巚偄傑偡丅偟偨偑偭偰丄夝偒捈偟傪偡傞偝偄偼丄戄庤偺寁嶼棙巕棪偑3.42%偲梌偊傜傟偰偄偨偲壖掕偟偰15暘埲撪偱偡傋偰偑夝摎偱偒傞傛偆偵偟偰偔偩偝偄丅
|
|
2013擭5寧崋晅榐乽曤婰丂儔僗僩125擔傪偳偆曌嫮偡傞偐丠乿
|
p.26丂戞堦栤丂栤2 A幮乮a乯 |
戄搢堷摉嬥偺夞摎偑TAC偺夝愢偱偼800,000偲側偭偰偄傑偡偑 杮晅榐偱偼2,000,000偲側偭偰偍傝傑偡丅側偤側偺偱偟傚偆偐丅
嵚尃偑傕偼傗懚嵼偟偰偄側偄乮丠乯偨傔慡妟庢傝曵偡偼偢側偺偵丄僉儍僢僔儏丒僼儘乕尒愊朄 偵偰尒愊傕傞偺偼晄帺慠側婥偑偟傑偡丅
|
杮晅榐偵偍偄偰丄俙幮偺巇栿乮倎乯偱戄搢堷摉嬥偺庢曵偟妟偑800,000墌偱偼側偔2,000,000墌偵側偭偰偄傞偺偼丄杮晅榐偱偼丄僨僢僩丒僄僋僀僥傿丒僗儚僢僾偺懳徾偲側偭偨庁擖嬥乮俙幮偵偲偭偰偼戄晅嬥乯偺晹暘偩偗偱側偔丄棙棪偑曄峏偝傟偨庁擖嬥乮俙幮偵偲偭偰偼戄晅嬥乯偵偮偄偰傕丄偦偺戄搢堷摉嬥傪丄堦搙偵庢曵偟偰偄傞偨傔偱偡丅丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂
側偍丄TAC偺夝愢偱偼丄(b)偵娭偡傞晹暘偱丄巆傝偺戄搢堷摉嬥乮1,200,000墌乯傪庢曵偟偰偄傑偡丅
傑偨丄夝愢偵偁傞乽乧嵚尃偼傕偼傗懚嵼偣偢乧乿偵偮偄偰偱偡偑丄偁偔傑偱乽摉婜傑偱乮傛傝惓偟偔偼亊4擭3寧31擔傑偱乯曐桳偟偰偄偨乮棙棪擭12%偺忦審偺乯嵚尃偼傕偼傗懚嵼偟偰偄側偄乿偲峫偊偰偄傑偡丅
偦偺偆偊偱丄亊4擭4寧1擔埲崀偼棙棪擭2%偺嵚尃120,000,000墌傪曐桳偟丄偦偺嵚尃偵娭偡傞戄搢堷摉嬥傪乽僉儍僢僔儏丒僼儘乕尒愊朄乿偵傛傝戄搢堷摉嬥傪寁忋偡傞偲峫偊偰偄傑偡丅
側偍丄挿婜戄晅嬥偲偄偆嵚尃偑乮搳帒桳壙徹寯偵揮姺偝傟偨晹暘傪彍偗偽乯扨偵乽戄搢寽擮嵚尃乿傊偲曄壔偟偨偩偗偲峫偊傞偺偱偁傟偽丄乮倎乯偱戄搢堷摉嬥偵偮偄偰偼800,000墌偺傒傪庢曵偟丄嵚尃120,000,000墌偵懳偟偰婛偵寁忋偝傟偰偄偨戄搢堷摉嬥1,200,000墌偵丄堷摉嬥梫愝掕妟乮嵚尃偐傜摼傜傟傞彨棃僉儍僢僔儏丒僼儘乕偲嵚尃偺妟柺嬥妟偺嵎妟乯偱偁傞28,821,975墌偲偺嵎妟27,621,975墌傪捛壛揑偵寁忋偡傞張棟偱偁偭偰傕丄娫堘偄偲偼偄偊偢乽亊乿偼偮偗側偄偼偢偱偡丅巇栿傪帵偣偽師偺傛偆偵側傝傑偡丅
(庁)戄搢堷摉嬥孞擖妟27,621,975丂(戄)戄搢堷摉嬥丂丂 27,621,975
偙傟偼丄TAC偵傛傞夝愢偺俙幮偺(倐)偺巇栿傪弮妟偱張棟偟偨傕偺偲傕峫偊傞偙偲偑偱偒傑偡丅
嵟屻偺乽側偍彂偒乿晹暘偼幹懌偐傕偟傟傑偣傫丅
|
|
2013擭4寧崋乽楢寢夛寁丂挻擖栧乿丂
|
p.9乣p.10
帒杮楢寢丒彮悢姅庡帩暘
彮悢姅庡偑偄傞応崌偺寁嶼
|
p.9傛傝乽恊夛幮偲彮悢姅庡偱丄巕夛幮偺弮帒嶻偵偍偗傞棙塿忚梋嬥偲昡壙姺嶼嵎妟摍傪暘偗崌偆偙偲偵側傞丅徻偟偔偼師儁乕僕偺椺戣傪尒偰偄偙偆丅乿 偲婰弎偟偰偁傝傑偡偑丄幚嵺偵師儁乕僕傪妋擣偟偨偲偙傠丄帒杮嬥丒帒杮忚梋嬥丒棙塿忚梋嬥乮偙偺栤戣偼昡壙姺嶼嵎妟摍偺嬥妟偼柍偄乯偺崌寁嬥妟偺俀侽亾傪彮悢姅庡帩暘偺嬥妟偲偟偰寁嶼偝傟偰偍傝傑偡丅
p.9偺暥復偲p.10偺寁嶼偑堦抳偟偰偄側偄偲巚偆偺偱偡偑丄偳偪傜偑惓偟偄偺偱偟傚偆偐丅
|
p.10偑惓偟偄偱偡丅
乽恊夛幮偲彮悢姅庡偱丄巕夛幮偺弮帒嶻偵偍偗傞棙塿忚梋嬥偲昡壙丒姺嶼嵎妟摍傪暘偗崌偆乿偲偄偆偺偼丄p.14埲崀偵彂偄偰偁傞丄楢寢偟偨師偺婜偐傜偺愢柧偵偐偐傞峫偊曽偱偡丅
撪梕偑娫堘偭偰偄傞傢偗偱偼側偄偺偱偡偑丄p.9偺僞僀儈儞僌偱彂偔傋偒偙偲偱偼側偐偭偨偐傕偟傟傑偣傫丅怽偟栿偛偞偄傑偣傫丅
楢寢奐巒帪偵偼丄
帒杮嬥丂丂丂丂30,000
帒杮忚梋嬥丂10,000
棙塿忚梋嬥丂11,000
偺崌寁51,000傪恊夛幮80%乮40,800乯偲巕夛幮20%乮10,200乯偱暘偗崌偄傑偡丅
偦偟偰丄楢寢偟偨師偺婜偐傜
帒杮嬥丂30,000仺30,000
帒杮忚梋嬥丂10,000仺10,000
棙塿忚梋嬥丂11,000仺14,000
偲側偭偨応崌丄棙塿忚梋嬥偺嵎妟晹暘14,000亅11,000亖3,000傪恊夛幮偲巕夛幮偱暘偗崌偄傑偡丅
|
|
2013擭3寧崋晅榐乽曤丒嵿寁嶼亊棟榑僟僽儖僩儗乕僯儞僌BOOK乿
|
p.20栤戣俆 栤俁 |
栤戣俆偺栤俁(尰暔弌帒偵傛傞桳宍屌掕帒嶻偺庢摼)偱偡偑丄尰暔弌帒偺応崌丄屌掕帒嶻偺庢摼尨壙偼乽庴偗擖傟偨屌掕帒嶻偺帪壙乿偱偼側偔丄乽弌帒幰偵懳偟偰岎晅偝傟偨姅幃偺帪壙乿偱偼側偄偱偟傚偆偐丅 |
暔弌帒偺応崌偼丄夛幮朄199忦侾崁3崋偱偼庴偗擖傟偨帒嶻偺壙妟偲婯掕偟偰偍傝傑偡丅
傑偨丄僗僩僢僋丒僆僾僔儑儞摍夛寁婎弨15崋偱偼丄庴偗擖傟偨帒嶻偺岞惓側昡壙妟乮帪壙乯偲敪峴偟偨姅幃偺岞惓側昡壙妟偺偆偪怣棅惈偺崅偄壙妟偲婯掕偟偰偍傝傑偡丅乮楢懕堄尒彂戞嶰偺婯掕偼揔梡偱偒側偔側傝傑偟偨乯
杮栤偼丄搚抧偵帪壙偑偁傝丄姅幃偵帪壙偑側偄乮幚幙壙妟乯偨傔搚抧帪壙傪庢摼尨壙偲偟傑偡丅
|
|
2013擭3寧崋乽戞132夞擔彜曤婰専掕帋尡侾媺丂栤戣偲柾斖夝摎丒夝愢乿
|
p.70
俁.嬥棙僗儚僢僾(孞墑僿僢僕夛寁揔梡乯
|
偙偙偵偁傞婜枛惍棟巇栿偵丄僗儚僢僾宊栺弮庴暐帪偺巇栿(庴庢嬥棙偲巟暐嬥棙偺嵎妟傪懝塿偲偟偰寁忋)
(庁)尰嬥丂丂丂丂丂丂 50丂
(戄)嬥棙僗儚僢僾懝丂 50
偑偁傝傑偣傫丅偙傟偼丄偳偺傛偆側棟桼偐傜偱偟傚偆偐丅
|
偛巜揈偺巇栿偼丄寛嶼惍棟帠崁侾丏偺①庁擖嬥棙懅300愮墌偺帺摦堷棊妟偺枹払帠崁偺張棟偵偍偄偰婛偵張棟嵪傒偲側偭偰偍傝傑偡丅偙傟偼丄
乮庁乯巟暐棙懅350愮墌丂
乮戄乯摉嵗梐嬥350愮墌
(10,000愮墌亊3.5亾亖350愮墌)
乮庁乯摉嵗梐嬥50愮墌丂
乮戄乯庴庢棙懅50愮墌
乮10,000愮墌亊乮3.5亾亅3.0亾乯亖50愮墌乯
丂丂丂丂丂丂伀丂丂丂丂丂丂丂丂
乮庁乯巟暐棙懅300愮墌丂
乮戄乯摉嵗梐嬥300愮墌
嬥棙僗儚僢僾偵傛傞嵎懝塿偼丄巟暐棙懅姩掕偱張棟偟傑偡丅
|
|
2013擭2寧崋晅榐乽側偤丄憤崌栤戣偑嬯庤側偺偐丠峌棯僈僀僪乿
|
p.16丂栤戣俀
|
A③乮p.17乯偺妱晩斕攧偵學傞夞廂晄擻帪偵偍偄偰丄戄搢堷摉嬥傪廩摉偟側偄偺偼側偤偱偟傚偆偐丅乮妱晩攧妡嬥偵傕戄搢堷摉嬥傪愝掕偟偰偄傞偲偁傝傑偡丅乯
|
偛巜揈偺偲偍傝丆戄搢堷摉嬥傪庢傝曵偡張棟傕峫偊傜傟傑偡偑丆崱夞偼丆庢栠偟彜昳懝幐偲偟偰張棟偡傞偙偲偵傛傝丆慜婜偵愝掕偟偨戄搢堷摉嬥傪偦偺傑傑巆偟偰丆摉婜偺孞擖妟偱挷惍偡傞張棟偱夝摎傪嶌惉偟傑偟偨丅
偳偪傜偑椙偄偲偄偆偙偲偼側偄偲巚偄傑偡偑丆偛巜揈偺張棟偱傕栤戣側偄偲巚偄傑偡丅
埲壓丄暿夝偵側傝傑偡丅
①20暸丂夝摎丂
丒戄搢堷摉嬥孞擖妟13,000愮墌
丒栠傝彜昳懝幐丂丂 丂800愮墌
②22暸丂夝愢 (3)夞廂晄擻崅偺廋惓巇栿
(庁)孞墑妱晩攧忋崅1,400愮墌丂
戄搢堷摉嬥丂 800愮墌
(戄)栠傝彜昳懝幐 丂2,200愮墌
③23暸丂夝愢 (2)堦斒嵚尃丂 ②惍棟巇栿
(庁)戄搢堷摉嬥孞擖妟6,000愮墌丂(戄)戄搢堷摉嬥 丂6,000愮墌
|
|
2013擭2寧崋晅榐乽側偤丄憤崌栤戣偑嬯庤側偺偐丠峌棯僈僀僪乿
|
p.50 栤戣俆
|
巇愗惛嶼彂偺巇栿偵偍偄偰丄庁曽乛慜庴嬥偺堄枴崌偄偼偳偺傛偆側庢堷傪慜採偲偟偰偄傞偺偱偟傚偆偐丅
壸堊懼偲偄偊偽丄
(庁)
(戄) |
|
尰嬥梐嬥丂
庤宍攧媝懝
攧妡嬥
攧忋
|
偲偄偆宍偑僆乕僜僪僢僋僗側巇栿偵側傞偲巚偄傑偡偑丄慜庴嬥傪庴戸幰偐傜傕傜偭偰偄偨偲偄偆慜採偵側傞偺偱偟傚偆偐丅
偦偆偡傞偲3幰娫偺庢堷偱側偔側傞偺偱丄堊懼庤宍偱偼側偄傛偆側婥偑偟傑偡丅
庢堷偺慜採傪帪宯楍偱嫵偊偰偄偨偩偗側偄偱偟傚偆偐丅
|
捠忢偺壸堊懼偺巇栿偼丄偛懚偠偺偲偍傝,
乮庁乯丂尰嬥梐嬥丂
庤宍攧媝懝
攧妡嬥丂丂
(戄乯攧忋
偲側傝傑偡丅
崱夞埾戸昳傪庴戸幰傊愊憲偟偨抜奒偱丆壸堊懼傪庢傝慻傓偙偲偑偁傝傑偡丅
(摿庩側壸堊懼偲屇傃傑偡乯
傛偭偰丆愊憲帪偵
(庁乯尰嬥梐嬥丂
庤宍攧媝懝
(戄乯慜庴嬥
偲偄偆巇栿傪偟偰偄傞偺偱丆攧忋寁忋帪偺乽壸堊懼庢慻妟乿偺偲偙傠偼丆庁曽偱慜庴嬥偺徚柵偲偟偰偄傑偡丅
|
|
2013擭1寧崋乽傑偄偵偪曤婰丂僗僥僢僾傾僢僾ver.乿
|
8暸丂夝摎 |
摿庩彜昳攧攦①偺夝摎乽俁丏婜枛彜昳扞壍崅3,600乿偼偳偆傗偭偰媮傔傞偙偲偑偱偒傞偺偱偟傚偆偐丅 |
丒婜枛彜昳扞壍崅3,600偺寁嶼
丂庤嫋彜昳偺婜枛彜昳2,000+婜枛愊憲昳800乮愊憲崅2,000亅攧忋尨壙1,200乯+帋梡昳枹攦庢堄巚昞帵暘800乮帋梡枹廂嬥巆崅1,200亐1.2亊0.8乯亖3,600
|
|
2013擭1寧崋晅榐乽嵿昞棟榑丂僗僥僢僾幃儚乕僋僽僢僋乿
|
p.9丂栤俇丂STEP3
|
嵿柋夛寁島媊偱偼丄廳梫側屻敪帠徾偺嬶懱椺偼俆偮偩偭偨偺偱偡偑丄懠偵傕偁傞偺偱偟傚偆偐丅
|
|
|
2013擭1寧椪帪憹姧崋乽寁嶼椡嫮壔BOOK乿幮嵚弮帒嶻偺晹
|
堦妵朄偵偮偄偰
p.75丂夝愢
p.85丂夝愢
|
p.75偺夝愢偱偼丄
乽堦妵朄偱偼丄怴姅梊栺尃晅幮嵚偲偟偰張棟偟傑偡丅乿偲偁傝傑偡偑丄p.85偺Step2偺堦妵朄偺夝愢偱偼丄戄曽偵幮嵚偑偁傝傑偡偑丄怴姅梊栺尃晅幮嵚偱傕惓偲側傝傑偡偐丅
偦傟偲傕丄夞摎偲偟偰偼幮嵚偱惓側偺偱偟傚偆偐丅
|
|
|
2013擭1寧椪帪憹姧崋乽寁嶼椡嫮壔BOOK乿奜壿寶庢堷
|
p.116
Step2 栤4
俼幮幮嵚
|
p.116偵偁傞R幮幮嵚偺恾昞偵偁傞婜枛彏媝尨壙偑俉俆僪儖偵側傞偐偑傢偐傝傑偣傫丅
偳偆偄偭偨寁嶼偺巇曽偩偭偨偺偱偟傚偆偐丅
|
丒R幮幮嵚偺婜枛彏媝尨壙偵偮偄偰栤戣暥拞偵巜帵偟偨傛偆偵丄R幮幮嵚偼摉婜庱偵敪峴偲摨帪偵庢摼偟偨傕偺偲峫偊傑偡丅
庢摼尨壙偼80僪儖偱妟柺嬥妟偼100僪儖偱偡丅偦偺嵎妟乮20僪儖乯偼嬥棙偺挷惍偲擣傔傜傟傞偺偱丄彏媝婜尷傪4擭娫偲偟偰彏媝尨壙朄乮掕妟朄乯傪揔梡偟傑偡丅丂傛偭偰丄20僪儖傪4擭偱妱傞偲枅婜枛偵5僪儖偢偮婜枛彏媝尨壙偑忋忔偣偝傟偰偄偔偙偲偵側傝傑偡丅偮傑傝丄埲壓偺傛偆偵側傝傑偡丅
庢摼帪80僪儖
1擭栚85僪儖佀崱夞偺婜枛彏媝尨壙
2擭栚90僪儖
3擭栚95僪儖
4擭栚100僪儖佀妟柺嬥妟偲側傞丅
側偍丄幃偱昞偡偲丄乮100僪儖亅80僪儖乯亐係亄80僪儖亖85僪儖偲側傝傑偡丅
|
|
|
|
|
2012擭12寧崋乽僴僀僷乕丒僩儗乕僯儞僌PLUS曤婰榑乿
|
栤2丂椺戣7乮116暸乣乯
俆丗攧忋尨壙偺夝摎乮119暸乯
|
攧忋尨壙偐傜尒杮昳旓偑堷偐傟偰偍傝傑偣傫偑丄傛傠偟偄偺偱偟傚偆偐丅 |
夝愢偱偺巇栿傪尨峞偺偲偍傝偵抳偟偨崻嫆偼丄亂帒椏2亃偺廋惓媦傃寛嶼惍棟帠崁摍乮堦晹乯偺側偐偱丄扞壍帒嶻偵偮偄偰偼丄俙彜昳偺乽摉婜偵尒杮昳偲偟偰棙梡偟偨彜昳偑17,600墌乮攧壙乯懚嵼偟偨偑丄壗偺婰榐傕峴傢傟偰偄側偄丅乿偲偄偆売強偱丄師偺巇栿傪偡偱偵峴偭偰偄傞偙偲偵婲場偟傑偡丅
丂丂偟偨偑偭偰丄寛嶼帪偺攧忋尨壙偺寁嶼偺抜奒偱偼丄尒杮旓偲偟偰巊梡偝傟偨俙彜昳偺彜昳巇擖崅偼丄偡偱偵彜昳巇擖崅偐傜峊彍偝傟偰偍傝傑偡偺偱丄攧忋尨壙偺寁嶼偱丄攧壙娨尦暯嬒尨壙朄偺娭學忋丄尒杮旓乮攧壙乯偑峊彍偝傟偨偩偗偱丄尒杮旓偵憡摉偡傞攧忋尨壙偺峊彍偑側偝傟偰偄側偄姶偠偑偁偭偨偲偟偰傕丄彜昳巇擖崅傪寁嶼偡傞夁掱偱偼丄妋幚偵峊彍偝傟丄揔惓側攧忋尨壙偑寁嶼偝傟傑偡丅
丂丂側偍丄杮審偺弌戣幰偺曽偺擣幆偵偼丄攧忋尨壙偺寁嶼偼丄寛嶼抜奒偱偡傋偰幚巤偡傋偒偱偁傞偲偄偆岆夝偑偁傞傛偆偵巚傢傟傑偡丅亂帒椏2亃偼廋惓媦傃寛嶼惍棟帠崁摍乮堦晹乯偲昞婰偝傟偰偍傝傑偡偟丄寛嶼惍棟偼丄婜拞庢堷偱偼揔惓偵張棟偱偒偰偄側偄帠崁偵偮偄偰挷惍傪偡傞偨傔偵峴偆巇栿傪巜偡偺偱偁偭偰丄偦傟偧傟偺巇栿偑撈棫偟偰偄傞傕偺偱偼偁傝傑偣傫丅
|
|
2012擭11寧崋乽僴僀僷乕僩儗乕僯儞僌徚旓惻朄乿
|
p.169
叀丂暯惉25擭1寧1擔偺壽惻婜娫偺擺惻媊柋偺桳柍偺敾掕
|
p.169
叀丂暯惉25擭1寧1擔偺壽惻婜娫偺擺惻媊柋偺桳柍偺敾掕
|
暯惉25擭侾寧侾擔乣暯惉25擭俁寧31擔壽惻婜娫偼柶惻帠嬈幰偵奩摉偟傑偡偐傜丄係亾壽惻攧忋偘偵偮偄偰偺惻敳張棟偼晄梫偲偄偆偙偲偵側傝傑偡丅
偟偨偑偭偰丄係亾壽惻攧忋偘偲柶惻攧忋偘偲傪暿乆偵寁嶼偟偰傕丄暘偗偢偵寁嶼偟偰傕寢壥偼曄傢傝傑偣傫丅杮帍偺夝摎偼丄係亾壽惻攧忋偘偲柶惻攧忋偘偲傪暿乆偵寁嶼偣偢偵丄旕壽惻攧忋偩偗傪彍奜偟偨嶼幃偱帵偟偰偁傝傑偡丅
|
2012擭10寧崋乽僴僀僷乕丒僩儗乕僯儞僌PLUS曤婰榑乿
|
121暸乣123暸偺栤戣 |
122暸偺栤戣暥偺嵟屻偵丄乽乮俉乯忋婰偺棤彂庤宍偍傛傃妱堷庤摉偼枮婜擔偵寛嵪偝傟偨乿偲偁傝傑偡偑丄偄偮寛嵪偝傟偨偑婰嵹偝傟偰偄側偄偺偱巹偼婜拞偲峫偊傑偟偨丅偦偺応崌丄曐徹嵚柋傪寁忋偟偰丄偦傟傪栠偟偄傟偡傞偲偄偆巇栿偼丄擭搙寛嶼偱偡偺偱偄傜側偄偺偱偼偲巚偄傑偡丅乮曐徹嵚柋旓梡偲曐徹嵚柋庢曵塿偑椉寶偰偵側偭偰朿傜傫偱偄傞乯
偙偪傜偼偳偺傛偆偵峫偊偨傜偄偄偺偱偟傚偆偐丅
|
夝愢偱偺巇栿傪尨峞偺偲偍傝偵偄偨偟偨崻嫆偼丄亂帒椏3亃偺昞婰偑乽婜拞庢堷媦傃寛嶼惍棟偵娭偡傞棷堄帠崁乿偲偁傞偙偲偵婲場偟傑偡丅偦偺偨傔丄偙偺応崌偵偼丄師偺傛偆側巇栿傪峴傢側偗傟偽側傝傑偣傫丅
枮婜擔寛嵪
乮庁乯曐徹嵚柋丂丂丂丂丂丂丂丂丂1,720
乮戄乯曐徹嵚柋庢曵塿丂丂丂 丂1,720
丂
|
|
2012擭10寧崋乽僴僀僷乕丒僩儗乕僯儞僌PLUS曤婰榑乿
|
113暸丂椺戣3
亂帒椏3亃乮3乯
|
亂戄搢堷摉嬥偺愝掕偺栤戣偵偮偄偰亃
偙偺栤戣偺拞偱丄113暸帒椏3偺側偐偵乮3乯2寧偵攧妡嬥偱庴偗庢偭偨彫愗庤傪嬧峴偱梐偗擖傟偡傞嵺丄岆偭偰戄庁傪媡偵巇栿偗偟偨偲偁傝傑偡丅
夝摎偱偼丄攧妡嬥岆婰挔偼丄
乮庁乯尰梐嬥丂924丂丂丂
乮戄乯攧妡嬥丂924丂
偲偁傝傑偡偑丄乬梐偗擖傟偺嵺偵岆偭偰戄庁傪媡偵偟偨乭偲偄偆偙偲偐傜丄俀寧偵攧妡嬥傪庴偗庢偭偨偲偒偼丄攧妡嬥夞廂偺巇栿傪偟偰偄傞偲悇掕偱偒壓婰偺巇栿偑悇應偱偒傑偡丅
乮庁乯尰梐嬥仺尰嬥丂462
乮戄乯攧妡嬥丂丂丂丂462
傑偨乮彫愗庤偼尰嬥乯
梐偗擖傟傞嵺偺岆巇栿偼丄壓婰偺巇栿偵側傞偺偱偼側偄偱偟傚偆偐丅
乮庁乯尰梐嬥仺尰嬥丂462
乮戄乯尰梐嬥仺摉嵗嬥丂462
偦偆偡傞偲丄廋惓巇栿偼丄壓婰偺傛偆偵側傞偲巚偄傑偡丅
乮庁乯尰梐嬥仺摉嵗嬥丂924
乮戄乯尰梐嬥仺尰嬥丂924
偦偺偨傔戄搢堷摉嬥偼6,470愮墌偵側傞偺偱偼側偄偱偟傚偆偐丅
|
丂夝愢偱偺巇栿傪尨峞偺偲偍傝偵偄偨偟偨崻嫆偼丄栤戣暥偑乽2寧偵攧妡戙嬥夞廂偱庴偗庢偭偨彫愗庤462愮墌乮惻崬傒乯傪嬧峴偵梐偗擖傟傞嵺丄岆偭偰戄庁傪媡偵巇栿偟偰偄偨丅乿偲偄偆偙偲偐傜丄杮棃偺偁傞傋偒巇栿偲幚嵺偵峴偭偨巇栿偑壓婰偺傛偆偵側偭偰偄傞偙偲偑妋掕偱偒傞偙偲偵婲場偟傑偡丅
乹杮棃偁傞傋偒巇栿乺
乮庁乯尰梐嬥丂丂丂462
乮戄乯攧妡嬥丂丂丂462
乹幚嵺偵峴偭偨巇栿乺
乮庁乯攧妡嬥丂丂丂462
乮戄乯尰梐嬥丂丂丂462
偟偨偑偭偰丄岆偭偰峴偭偨巇栿偺掶惓乮庢徚乯偲杮棃偁傞傋偒巇栿偺捛壛傪峫偊傞偲丄尨峞偵帵偟偨廋惓巇栿偺傛偆偵側傝傑偡丅
丂
|
|
2012擭8寧崋晅榐乽挻儕傾儖柾帋乿
|
20暸
栤俀
|
丂[枮婜曐桳栚揑桳壙徹寯]偲[偦偺懠桳壙徹寯]偑俆儠強桳傝傑偡丅
姩掕壢栚偱側偔夛寁梡岅偱偼側偄偱偟傚偆偐丅
|
嵿柋彅昞傪嶌惉偡傞応崌偵偼乽搳帒桳壙徹寯乿偱偡偑丄杮栤偱偼巇栿傪栤偆偰傑偡偺偱丄偦偙偱偺姩掕壢栚偼夝摎捠傝偱傕乽搳帒桳壙徹寯乿偱傕偄偢傟偱傕嫋梕偝傟傞偺偑幚忣偲巚傢傟傑偡丅
偲偼偄偊丄庴尡栤戣廤側偳偱偼曤婰榑偺巇栿栤戣偱傕乽搳帒桳壙徹寯乿偲偟偰偄傞応崌偑懡偄傛偆偱偡偺偱丄偦偺揰傪摜傑偊偰乽搳帒桳壙徹寯乿傪夝摎偵帵偟偨曽偑朷傑偟偐偭偨傛偆偵巚傢傟傑偡丅帋尡捈慜偵崿棎傪彽偒傑偟偨偙偲偍榣傃偡傞偲摨帪偵丄杮帋尡偱偺偛寬摤傪婩擮偄偨偟傑偡丅
|
|
2012擭7寧崋晅榐乽憤崌栤戣偱僠僃僢僋偡傞乬120亾偱傞榑揰乭乿
|
p.26
憤崌栤戣俁
|
亂帒椏侾亃偺慜T/B偺戄曽偵丄亀庴庢庤宍2,000亁偲偁傝傑偡偑丄庴庢庤宍偑戄曽巆崅偵側傞偲偄偆僀儊乕僕偑偮偒傑偣傫丅
丂栤戣偺巜帵偵丄嬥妟偺岆張棟偲偄偆偺傕柍偄偺偱丄偳偆偄偆働乕僗偱庴庢庤宍偑戄曽巆崅偵側傞偺偐偵偮偒傑偟偰丄偛夝愢傪捀懻偱偒傟偽岾偄偱偡丅
|
2012擭7寧崋晅榐丂憤崌栤戣俁偵偮偄偰
庴庢庤宍姩掕偺戄曽巆崅偵偮偄偰偱偡偑丆庴庢庤宍偵娭偟偰惍棟慜T/B偵枹婰挔側偺偼丆3寧拞偺庴庢庤宍敪惗偵娭偡傞庢堷偺傒偱偡丅偟偨偑偭偰丆3寧拞偵庴庢庤宍偺寛嵪偵娭偡傞庢堷偼捠忢捠傝婰挔偝傟偰偄傑偡丅
偮傑傝丆乽婜庱庴庢庤宍亄4寧偐傜2寧傑偱偺庴庢庤宍敪惗妟亙4寧偐傜3寧傑偱偺庴庢庤宍寛嵪妟乿偲偄偆忬懺偺偨傔偵丆偨傑偨傑庴庢庤宍姩掕偑戄曽巆崅偵側偭偰偄傑偡丅
3寧拞偺庴庢庤宍敪惗庢堷偑婰榐偝傟偰偄側偄偨傔丆応崌偵傛偭偰偼偙偺傛偆側働乕僗傕惗偠傞偙偲偵側傝傑偡丅
|
|
2012擭俈寧椪帪憹姧崋乽偱傞弴儔儞僉儞僌BEST10乿
|
24暸
塃抜丂忋偐傜係峴栚偵偁傞(2)婜枛姺嶼偺巇栿
|
24暸丂塃抜丂忋偐傜係峴栚偵偁傞(2)婜枛姺嶼偺巇栿偺偆偪丄
(庁)堊懼嵎懝塿455丂(戄)搳帒桳壙徹寯455
偺455偼450偱偼側偄偺偱偟傚偆偐丅
|
堊懼嵎懝455偺寁嶼庤弴偼師偺捠傝偱偡丅
彏媝尨壙朄偺揔梡偵傛傝C幮幮嵚僪儖儀乕僗曤壙偼丄 丂丂 丂丂丂丂 150愮暷僪儖亄1愮暷僪儖亖151愮暷僪儖
彏媝尨壙朄偺揔梡偵傛傝C幮幮嵚墌儀乕僗曤壙偼丄
150愮暷僪儖亊HR@83墌亄85愮墌亖12,535愮墌
僪儖儀乕僗曤壙151愮暷僪儖亊CR@80墌亅墌儀乕僗曤壙12,535墌亖仮455乮堊懼嵎懝乯
|
|
2012擭7寧崋晅榐乽憤崌栤戣偱僠僃僢僋偡傞乬120%偱傞榑揰乭乿
|
憤崌栤戣5 夝愢
59暸
|
寶暔偺帒杮揑巟弌偺寁嶼偱丄夝愢59暸偺夝摎偺億僀儞僩偵丄乽乮拲乯巆懚壙妟偼帒杮揑巟弌偺懳徾帒嶻偺帒杮揑巟弌帪偺曤壙媦傃帒杮揑巟弌妟偺崌寁妟偺10%偱偁傞丅乿偲夝愢偝傟偰偍傝傑偡偑丄巆懚壙妟偼丄庢摼壙妟偺10%偱寁嶼偡傞偺偱偼側偄偱偟傚偆偐丠
|
亂帒杮揑巟弌妟屻偺尭壙彏媝旓偺寁嶼偵偮偄偰亃
巆懚壙妟偵偮偄偰偼丄庢摼尨壙偲帒杮揑巟弌妟偺崌寁偺侾侽亾偑堦斒揑偱偡偑丄帒杮揑巟弌帪偺曤壙偲帒杮揑巟弌妟偺侾侽亾傪怴偨側巆懚壙妟偲偡傞応崌偑偁傝傑偡丅
崱夞偺栤戣偼巜帵偵傛傝曤壙偲帒杮揑巟弌妟偺崌寁偺侾侽亾傪巆懚壙妟偲偡傞偲偁傞偺偱丄偦傟偵廬偭偰尭壙彏媝旓偺寁嶼傪峴偄傑偡丅摿偵巜帵偑側偄応崌偵偼丄庢摼尨壙偲帒杮揑巟弌妟偺崌寁妟偺侾侽亾傪巆懚壙妟偲偟偰寁嶼偟偰栤戣偁傝傑偣傫丅
|
|
2012擭7寧崋晅榐乽憤崌栤戣偱僠僃僢僋偡傞乬120亾偱傞榑揰乭乿
|
11暸丒13暸
|
13暸偵丄帺屓怴姅梊栺尃偺昡壙偺忦審偲偟偰丄俀偮偁偘傜傟偰偄傑偡偑丄偙偺忦審俀偮偲傕傪枮偨偡昁梫偑偁傞偺偱偟傚偆偐丅
傑偨丄偁傞応崌丄11暸偺栤戣偵偍偄偰偳偺晹暘偑奩摉偡傞偺偱偟傚偆偐丅
|
仠晅榐偺審
帺屓怴姅梊栺尃偺昡壙偵偮偄偰帺屓怴姅梊栺尃偺昡壙懼偊傪峴偆嵺偵偼丆師偺庢埖偄偲側傝傑偡乮慜採忦審丗怴姅梊栺尃偺敪峴壙妟傛傝傕帺屓怴姅梊栺尃偺庢摼尨壙偑崅偄応崌乯丅
偦偺侾丗曐桳偡傞帺屓怴姅梊栺尃傪張暘偟側偄乮帩偪懕偗傞俷俼徚媝乯
偙偺応崌偼敪峴偟偰偄側偄偺偲摨偠側偺偱丆帺屓怴姅梊栺尃傪怴姅梊栺尃偺敪峴壙妟偵昡壙懼偊偟傑偡丅偮傑傝丆帺屓怴姅梊栺尃偲懳墳偡傞怴姅梊栺尃偺嬥妟偑摨妟偵側傝丆幚幙揑偵僛儘偵側傝傑偡丅
偦偺俀丗曐桳偡傞帺屓怴姅梊栺尃傪張暘偡傞応崌
偙偺応崌偼帪壙偑挊偟偄壓棊偱夞暅偺尒崬偑側偄偙偲偑捛壛忦審偲側傝傑偡丅偙偺応崌偺昡壙曽朄偼俀偮偁傝傑偡丅
①怴姅梊栺尃偺敪峴壙妟亜帺屓怴姅梊栺尃偺帪壙偺応崌
偙偺偲偒丆帺屓怴姅梊栺尃傪帪壙偵昡壙懼偊偟偰偟傑偆偲丆懳墳偡傞怴姅梊栺尃偑巆偭偰偟傑偆偺偱丆怴姅梊栺尃偺敪峴壙妟乮忋婰偦偺侾偲摨偠乯偵昡壙懼偊傪峴偄傑偡丅
②怴姅梊栺尃偺敪峴壙妟亙帺屓怴姅梊栺尃偺帪壙偺応崌
偙偺応崌偼丆帪壙偱昡壙懼偊傪峴偆偙偲偵側傝傑偡乮懳墳偡傞怴姅梊栺尃偼帺屓怴姅梊栺尃偱峊彍偟偒偭偰偟傑偆偨傔乯丅
愢柧偑挿偔側偭偰偟傑偄傑偟偨偑丆億僀儞僩偲偟偰偼帺屓怴姅梊栺尃傪張暘偟丆帪壙偺壓棊偑偁傝丆怴姅梊栺尃偺敪峴壙妟傛傝傕帪壙偑崅偄応崌偵偺傒帺屓怴姅梊栺尃傪帪壙昡壙偡傞偙偲偵側傝傑偡丅
|
|
2012擭俈寧崋晅榐乽憤崌栤戣偱僠僃僢僋偡傞乬120亾偱傞榑揰乭乿
|
59暸
乮侾乯尭壙彏媝旓偺寁嶼乮a乯寶暔
乮儘乯尭壙彏媝旓偺寁嶼
|
帒杮揑巟弌偺拞偺嶼弌幃偵偮偄偰偛幙栤偝偣偰偔偩偝偄丅
偙偺嶼弌幃偺売強偵丄乽6,500墌乮巆懚壙妟乯乿偑偁傞偺偱偡偑丄偦偺6,500墌偼枹徚媝巆崅偺60,000偲帒杮揑巟弌妟5,000偺侾侽亾側偺偱偟傚偆偐丅
巹偼丄寶暔偺曤壙偱偁傞150,000墌偺巆懚壙妟偺10亾偲帒杮揑巟弌妟5,000偺10亾偱15,500墌偵側傞偺偱偼側偄偐偲巚偭偰偍傝傑偟偨丅
偦偺偨傔夝摎偑乽6,500墌乮巆崅壙妟乯乿偲側傞崻嫆傪偛嫵庼偔偩偝偄丅
|
帒杮揑巟弌屻偺尭壙彏媝偵偮偄偰
婎杮揑偵帒杮揑巟弌慜偲帒杮揑巟弌屻偺尭壙彏媝寁嶼偑曄傢偭偰偟傑偆偺偱丆帒杮揑巟弌帪揰偺枹彏媝巆崅偲帒杮揑巟弌妟偺崌寁妟傪儀乕僗偵巆懚壙妟傪寛掕偡傞偺偑懨摉偱偡丅
偨偩偟丆栤戣偵柧妋側巜帵偑偁傟偽偦傟偵廬偆偙偲偵側傝傑偡丅
|
|
2012擭7寧椪帪憹姧崋乽偱傞弴儔儞僉儞僌BEST10丂曤婰榑乿
|
15暸
|
①惻岠壥夛寁偺戅怑媼晅堷摉嬥偺張棟偑傛偔傢偐傝傑偣傫丅
|
①摉婜枛偺乽堦帪嵎堎乿偲偟偰偺戅怑媼晅堷摉嬥孞擖挻夁妟偲偄偆帒椏偱偁傞側傜丄偦傕偦傕堦帪嵎堎偼丄夛寁忋偲惻柋忋偺帒嶻晧嵚偺嵎妟偱偡偐傜椵寁偲峫偊傞傋偒偱偟傚偆丅
杮栤偼摉婜枛偺乽惻柋挷惍崁栚乿偲偟偰偺戅怑媼梌堷摉嬥孞擖挻夁妟偲偄偆帒椏偺梌偊曽偱偡丅偮傑傝丄惻柋忋戅怑媼乽梌乿堷摉嬥偺孞擖偑攑巭偝傟偨偺偵夛寁忋偼孞傝擖傟偨偨傔丄壛嶼挷惍偟偨妟傪堄枴偟偰偍傝丄摉婜偵怴偨偵敪惗偟偨嵎堎偲峫偊傞傋偒偱偡丅
|
|
②忋婰夞摎偵偮偄偰偺幙栤偱偡丅
攑巭偝傟偨傕偺傪孞擖傟偨帪偼丄廋惓嵞昞帵偟偨傝丄戅怑媼晅堷摉嬥偵嵞寁嶼偟偨傝偼偟側偄偺偱偟傚偆偐丅
傑偨丄戅怑媼梌堷摉嬥偵側傞偲丄怴偨側孞擖偵側傞偲偄偆偺傕傛偔傢偐傝傑偣傫丅
|
②傑偢戅怑媼梌堷摉嬥惂搙偺攑巭偼丄朄恖惻朄忋偺夵惓偱偁傝丄夛寁忋偺曄峏偱偼偁傝傑偣傫丅
偡側傢偪丄夛寁忋偼戅怑媼晅旓梡傪寁忋偡傞偺偼帺桼偱丄惻柋怽崘彂忋偵偍偄偰丄戅怑媼梌堷摉嬥孞擖妟傪懝嬥晄嶼擖偡傞偙偲偵側傝傑偡丅
師偵丄戅怑媼梌堷摉嬥孞擖挻夁妟偼丄摉婜偵偍偄偰夛寁忋偺戅怑媼晅旓梡偺偆偪丄戅怑媼梌堷摉嬥孞擖妟偵憡摉偡傞妟傪懝嬥晄嶼擖偟偨偙偲傪堄枴偟偰偍傝丄偙偙偐傜椵寁偱偼側偔丄摉婜偺怴偨側孞傝擖傟暘偱偁傞偙偲傪撉傒庢傞昁梫偑偁傝傑偡丅
|
|
2012擭6寧崋楢嵹乽乽桳曬乿偐傜杹偔嵿柋夛寁椡乿
|
p.54 栤戣
|
帒椏俀丏乮俀乯偵丄亀惓枴偺孞墑惻嬥帒嶻偺偆偪20%偼夞廂晄擻亁偲偁傝傑偡丅
丂偦偙偱丄p.55偺夝愢偱偼丄
(庁) 朄恖惻摍挷惍妟丂119 (戄) 孞墑惻嬥帒嶻丂 119
丂偲偄偆巇栿偑偒傜傟偰偍傝傑偡偑丄側偤庁曽偑亀朄恖惻摍挷惍妟119亁偵側傞偐偑棟夝偱偒偰偍傝傑偣傫丅
丂側偤側傜丄惓枴偺孞墑惻嬥帒嶻595偺偆偪丄70偼 偦偺懠桳壙徹寯昡壙嵎妟偐傜 惗偠偰偄傞偺偱丄夞廂晄擻暘偵娭偡傞巇栿偼丄壓婰偺傛偆偵側傞偲峫偊偰偟傑偆偺偱偡丅
(庁)
(戄) |
|
朄恖惻摍挷惍妟
偦偺懠桳壙徹寯
昡壙嵎妟嬥 丂
孞墑惻嬥帒嶻丂
|
|
105丂
14仸
119丂
|
|
|
仸14=70亊20 亾 |
丂偦傟偲傕丄孞墑惻嬥帒嶻乮晧嵚乯偑夞廂晄擻偲側傞嵺偼丄
昁偢憡庤姩掕偼朄恖惻摍挷惍妟偩偗偲側傝丄偦偺懠桳壙徹寯昡壙嵎妟嬥偑棃傞偙偲偼側偄丄偲妎偊偰偍偗偽丄娫堘偄側偄偲偄偆偙偲側偺偱偟傚偆偐丠
|
偛巜揈偺庯巪偼椙偔傢偐傝傑偡丅
杮栤偱傕夞廂晄擻晹暘偑偳偙偐傜惗偠偰偄傞偐偑晄柧偱偁傞偺偱丆偦偺懠桳壙徹寯昡壙嵎妟嬥晹暘傪夞廂晄擻偐偳偆偐偑敾抐偱偒傑偣傫丅
偨偩丆偦偺懠桳壙徹寯昡壙嵎妟嬥偵學傞孞墑惻嬥帒嶻偵偮偄偰夞廂晄擻偲偟偨応崌丆夝摎悢抣偵奩摉偡傞慖戰巿偑側偄偙偲偐傜丆慡妟夞廂壜擻偱偁傞偲峫偊偰張棟偟傑偡丅
側偍丆夞廂晄擻偲尒崬傑傟偨応崌偵偼丆偛巜揈偺偲偍傝摉奩嬥妟傪昡壙嵎妟偵壛尭偟偰張棟偡傞偙偲偲側傝傑偡丅
|
|
2012擭6寧崋晅榐乽堦婥偵崌奿僩儗乕僯儞僌77栤乿
|
16暸丒18暸
|
16暸偺敪惗庡媊偺尨懃偵偮偄偰丄偛幙栤偝偣偰偔偩偝偄丅
栤戣3偺夝摎3乣4峴栚乽楯摥偺採嫙傪婇嬈偑旓徚偟偨偙偲乿偲栤戣4偺夝摎偺2乣3峴栚乽楯摥傪採嫙偟丄婇嬈偼偙傟傪徚旓偟偰偍傝乿偼乽旓徚乿偲乽徚旓乿偲偄偆尵梩傪巊偄暘偗偰偄傑偡偑丄
偙偺巊偄暘偗偺婎弨偼壗偱偟傚偆偐丠偦傟偲傕丄傑偭偨偔摨偠堄枴偱偟傚偆偐丠
18暸偺寠杽傔匓偺夝摎偼乽旓徚乿偱偡偑丄壖偵摨偠堄枴偩偲偟偨帪丄乽徚旓乿偱偼晄惓夝側偺偱偟傚偆偐丅
|
丂旓徚偲徚旓偺堘偄偱偡偑丆杮晅榐偱偼丆婎杮揑偵偼丆乽旓徚乿傪巊偭偰偄傑偡丅
丂偱偼丆側偤丆旓徚傪巊偭偰偄傞偐偲偄偆偲徚旓偲旓徚偼丆埲壓偺傛偆偵嬫暿偡傞偙偲偑偱偒傑偡丅丂
丂徚旓偼丆暔幙揑側尭彮帺懱傪偲傜偊偨梡岅偲偟偰峫偊偰偍傝傑偡丅偨偲偊偽丆彜昳侾屄傪攧傝忋偘偰丆堷偒搉偟偨側傜偽丆暔帒揑偵侾屄偺彜昳偑柍偔側偭偰偍傝傑偡丅偙偺傛偆偵暔帺懱偑柍偔側偭偨応崌偵偼丆徚旓偲偟偰偲傜偊偰偄傑偡丅
丂旓徚偼丆壙抣揑側尭彮帺懱傪偲傜偊偨梡岅偲偟偰峫偊偰偍傝傑偡丅偨偲偊偽丆彜昳侾屄傪攧傝忋偘偰丆堷偒搉偟偨偲偟偰傕丆壙抣偑柍偔側傝丆攧忋尨壙偲偟偰旓梡寁忋偡傞嬥妟偼丆愭擖愭弌朄傗暯嬒朄側偳偺暐弌扨壙傪揔梡偟偰嶼掕偟傑偡丅偮傑傝丆旓徚偼丆壙抣偑柍偔側偭偨暘傪嬥妟揑偵偲傜偊偰偄傑偡丅
丂偙偺傛偆偵丆徚旓偲旓徚傪偲傜偊偰偄傑偡丅
丂丂偱偼丆偙偺傛偆偵丆尩枾偵偲傜偊傞昁梫偼偁傞偺偐偲偄偊偽丆偄傠偄傠側妛幰偺愭惗偺僥僉僗僩傪撉傓尷傝丆尩枾偵暘偗偰偄傞僥僉僗僩傕偁傟偽丆尩枾偵暘偗偰偄側偄僥僉僗僩傕偁傝丆偐側傝丆濨枂偵彂偐傟偰偄傑偡丅
丂丂偱偼丆夛寁婎弨偺儗儀儖偱偼丆偳偺傛偆偵梡偄傜傟偰偄傞偐偲偄偆偲丆
丒僗僩僢僋丒僆僾僔儑儞偺夛寁婎弨偼乽徚旓乿偲偄偆梡岅偑梡偄傜傟偰偄傑偡(僗僩僢僋丒僆僾僔儑儞夛寁婎弨戞35崁)丅
丒帒嶻彍嫀嵚柋偺夛寁婎弨偱偼丆乽旓徚乿偲偄偆梡岅偑梡偄傜傟偰偄傑偡(帒嶻彍嫀嵚柋夛寁婎弨戞32崁)丅
丒扞壍帒嶻偺昡壙偵娭偡傞夛寁婎弨偱偼丆乽徚旓乿偲偄偆梡岅偑梡偄傜傟偰偄傑偡(扞壍帒嶻偺昡壙偵娭偡傞夛寁婎弨戞28丒29崁)丅
丂偙偺偆偪丆帒嶻彍嫀嵚柋偺乽旓徚乿偼壙抣偑柍偔側偭偨晹暘傪嬥妟揑偵偲傜偊偰偄傞偲峫偊傜傟丆扞壍帒嶻偺乽徚旓乿偼乽帠柋梡徚栒昳偺抁婜揑側徚旓乿偲偄偆暥柆偐傜丆暔幙揑側尭彮傪偲傜偊偰偄傞偲峫偊傜傟傑偡丅
丂偟偐偟側偑傜丆僗僩僢僋丒僆僾僔儑儞偱梡偄傜傟偰偄傞乽徚旓乿偲偄偆梡岅偺傒丆廬嬈堳偑採嫙偟偨楯摥僒乕價僗偺壙抣揑尭彮傪巜偡偲峫偊傜傟傞偵傕偐偐傢傜偢丆乽徚旓乿偲偄偆梡岅傪梡偄偰偄傑偡丅偟偨偑偭偰丆偙偺僗僩僢僋丒僆僾僔儑儞偺夛寁婎弨偺寠杽傔栤戣偑弌戣偝傟偨応崌偩偗偼丆拲堄偑昁梫偱偡丅
丂偦偺懠偺応崌偵偼丆傎偲傫偳丆乽旓徚乿偲偄偆梡岅偑摉偰偼傑傝傑偡丅偨偲偊偽丆帋尡埾堳偺愭惗偑嶌傜傟偨暥復偱偁傟偽丆乽旓徚乿偱傕乽徚旓乿偱傕偐傑傢側偄偲峫偊傑偡丅
丂埲忋丆寢榑傪傑偲傔傑偡偲
丂①丂暔幙揑側尭彮偼丆乽徚旓乿偲偟偰丆壙抣揑側尭彮偼丆乽旓徚乿偲偟偰峫偊傞偺偑傛偔丆帒嶻彍嫀嵚柋傗偦偺懠偺帋尡埾堳偺愭惗偑嶌傜傟偨暥復偱偼丆偱偒傞偩偗乽旓徚乿偺曽偑傛偄丅
丂②丂僗僩僢僋丒僆僾僔儑儞夛寁婎弨偺寠杽傔栤戣偩偗偼丆偱偒傞偩偗乽徚旓乿偺曽偑傛偄丅僗僩僢僋丒僆僾僔儑儞偺榑弎栤戣偱偼偲偄偆偲丆傕偟傕乽旓徚乿傪梡偄偨偲偟偰傕丆昁偢偟傕亊偵偼側傜側偄偲峫偊傜傟傞丅
丂偲側傝傑偡丅側偐側偐丆僥僉僗僩儗儀儖偱偼丆柧妋偵巊偄暘偗傜傟偰偄側偄梡岅偱偁偭偰丆夛寁婎弨偺暥尵偲偟偰偼丆摑堦偝傟偰偄側偄梡岅側偺偱丆愢柧偟偒傟偢丆棟夝偑擄偟偐偭偨偲巚偄傑偡丅
|
|
2012擭4寧崋乽愴棯揑乽曤丒嵿乿妛廗僫價乿
|
p.33丂栤戣俋
|
①峸擖偟偨婡夿憰抲傪帠嬈偺梡偵嫙偡傞偨傔偺帋塣揮旓 偲②峸擖偟偨塩嬈強梡寶暔偺庢摼偵學傞搊榐柶嫋惻 偼丄屌掕帒嶻庢摼帪偺晅悘旓梡偱偁傞偨傔丄婡擻偺夵慞傪栚揑偲偡傞帒杮揑巟弌偵偼奩摉偟側偄偲巚偆偺偱偡偑偄偐偑偱偟傚偆
偐丠
|
弌戣偼丄帒嶻張棟偝傟傞傕偺偲旓梡張棟偝傟傞傕偺偺嬫暿傪栤偆傕偺偱偡丅
堦斒偵屌掕帒嶻偵學傞巟弌偺偆偪乮庢摼帪傕娷傔偰乯帒嶻偲偟偰張棟偝傟傞巟弌偑帒杮揑巟弌偱偡丅
屼巜揈偺帋塣揮旓傗搊榐柶嫋惻傕帒杮揑巟弌偵側傝傑偡丅
偦偺婜偺旓梡偲偟偰張棟偡傞偐乮廂塿揑巟弌乯丄偄偭偨傫帒嶻偺庢摼尨壙偵娷傔偰丄偦偺屻偺婜娫偵旓梡壔偟丄屻偺懝塿寁嶼偵娷傔傞偐偑嬫暿偺昗弨偱偡丅
屌掕帒嶻娭楢偺巟弌偵偮偄偰偼丄庢摼屻偺夵廋帪偺巟弌偑栤戣偲側傞偙偲偑懡偄傛偆偱偡丅
偙偺応崌偵偼丄屼巜揈偺傛偆偵屌掕帒嶻偺壙抣傪崅傔丄棙梡壜擻婜娫傪墑挿偝偣傞巟弌偑帒杮揑巟弌偵側傝傑偡丅
|
|
2012擭4寧崋乽惓峌朄偺乽曤婰椡乿摿孭僗僋乕儖乿
|
p.52丂夝愢丂
7丏弨旛嬥媦傃帺屓姅幃偺(2)拞娫攝摉偵偮偄偰
|
夝愢偵偁傞廋惓巇栿偵偼丄 攝摉帪偺弨旛嬥偺愊傒棫偰張棟偑偝傟偰偍傝傑偣傫偑丄 愊傒棫偰偺昁梫偑柍偄偺偱偟傚偆偐丠
偮傑傝丄弨旛嬥偺愊傒棫偰傪峫椂偡傟偽丄壓婰偺傛偆側廋惓巇栿偑惓偟偄偺偱偼側偄偐偲巚偄傑偡丅
(庁)偦偺懠帒杮忚梋嬥
3,300
(戄) 帒杮弨旛嬥丂丂300丂棙塿弨旛嬥 300
丂孞墇棙塿忚梋嬥2,700
|
拞娫攝摉偵學傞弨旛嬥偺愊棫偱偡偑丆弨旛嬥偑帒杮嬥偺4暘偺1傪挻夁偟偰偄傞応崌偵偼愊棫偼晄梫偱偡丅
崱夞偼弨旛嬥崌寁偑帒杮嬥偺4暘偺1傪挻夁偟偰偄傞偨傔丆弨旛嬥偺愊棫偼晄梫偲側傝傑偡丅
側偍丆栤戣偺帒椏俋偵偍偄偰丆弨旛嬥偺尭彮庤懕傪峴偭偰偄傑偡偑丆偦傟偱傕帒杮嬥偺係暘偺侾傪挻偊偰偄傞偨傔丆寢壥揑偵愊棫嬥偺寁忋偼晄梫偲側傝傑偡丅
①帒杮嬥偺係暘偺侾
200,000愮墌亊侾乛係亖50,000愮墌
②弨旛嬥偺崌寁妟
100,000愮墌乮惍棟慜俿乛俛偺帒杮弨旛嬥乯亄25,000愮墌乮惍棟慜俿乛俛偺棙塿弨旛嬥乯亅50,000愮墌乮帒杮弨旛嬥偺尭彮妟乯亅20,000愮墌乮棙塿弨旛嬥偺尭彮妟乯亖55,000愮墌
③丂①亙②丂傛偭偰丆弨旛嬥偺愊棫偼晄梫偱偡丅
|
|
夛寁恖僐乕僗2012.1崋乽僴僀僷乕丒僩儗乕僯儞僌PLUS丂曤婰榑乿
|
p.107
尭懝傪揔梡屻偺尭壙彏媝旓偵偮偄偰
|
尭懝張棟屻偵尭壙彏媝張棟傪偡傞巪偺夝愢偑偁傝傑偡偑丄尨懃揑側張棟偺弴彉偲偟偰偼丄尭壙彏媝張棟屻偵尭懝張棟傪峴偆偺偑惓偟偄偺偱偼側偄偱偟傚偆偐丠
乮偪側傒偵丄杮栤 椺戣6偺夝摎偵帵偝傟偰偄傞尭懝張棟偺悢抣偼丄 寶暔A偺摉婜暘偺尭壙彏媝張棟幚巤屻偺 悢抣偲側偭偰偄傞偲巚偄傑偡丅乯
|
|
|
2011擭11寧崋乽愴棯揑亀曤丒嵿亁妛廗僫價乿
|
70暸
栤戣侾③偵偮偄偰
|
①杮栤戣偵偰丄C幮偼恊夛幮姅幃偵奩摉偟丄昡壙偼帪壙偱峴傢傟傞偲偁傝傑偡偑丄巹偑傗偭偨栤戣偱偼丄恊夛幮姅幃偼尨壙偵偰張棟傪偟偰偄傑偟偨丅偙傟偼丄愄偐傜帪壙偩偭偨偺偱偟傚偆偐丅
偦傟偲傕丄尨壙偐傜帪壙偵側偭偨偺偱偟傚偆偐丅
|
①嬥梈彜昳偺夛寁婎弨乮暯惉侾俀擭乯偑偱偒傞埲慜偼丄桳壙徹寯帺懱偑尨壙昡壙偱偟偨丅 偦偙偐傜帪壙昡壙偵曄傢偭偰偄傑偡丅偨偩丄悘暘偲慜偺榖側偺偱丄楢寢嵿柋彅昞忋偺榖偐傕偟傟傑偣傫丅恊夛幮姅幃偼丄屄暿嵿柋彅昞忋偼帪壙昡壙偱偡偑丄楢寢嵿柋彅昞忋偼尨壙昡壙偱偡丅
|
|
②恊夛幮姅幃偑帪壙側偺偼丄恊夛幮姅幃偺張棟偑帪壙偩偐傜側偺偱偟傚偆偐丅偦傟偲傕昡壙忋偺嬫暘偑丄偦偺懠桳壙徹寯偩偐傜帪壙偵側傞偺偱偟傚偆偐丅
|
②恊夛幮姅幃偼丄屄暿嵿柋彅昞忋丄嬥梈彜昳偵娭偡傞夛寁偵傛傝丄昡壙忋偺嬫暘偵偟偨偑偭偰昡壙偡傞偙偲偵側傝傑偡丅
恊夛幮姅幃偼丄攧攦栚揑桳壙徹寯偐丄偦偺懠桳壙徹寯偵奩摉偟傑偡偑丄偄偢傟偺応崌傕帪壙偱昡壙偝傟傑偡丅
|
|
夛寁恖僐乕僗2011.8崋乽僴僀僷乕丒僩儗乕僯儞僌丂曤婰榑乿
|
倫.79乣80
杮幮岺応夛寁
|
婜枛巇妡昳丄惢昳偺偦傟偧傟偺嵽椏旓丄 壛岺旓偺悢抣偵偮偄偰徻弎偟偰偄偨偩偗傞偲岾偄偱偡丅
嬶懱揑偵偼丄
丒婜枛巇妡昳搳擖壛岺旓丂296,450墌
丒婜枛惢昳摉婜姰惉昳搳擖嵽椏旓丂413,600墌
丒摉婜姰惉昳壛岺旓丂310,400墌丂
摍偺悢抣崻嫆偑暘偐傜偢擸傫偱偍傝傑偡丅
|
恾夝傪偛婓朷偝傟偰偍傝傑偟偨偑丆2011擭8寧崋偵偰恾傪帵偟偰偍傝傑偟偨偺偱丆傕偭傁傜丆寁嶼幃偲悢抣偺崻嫆偵偮偄偰愢柧偝偣偰偄偨偩偒傑偟偨丅
徻嵶偼丄偙偪傜偐傜偛棗偔偩偝偄丅
|
|
2011擭10寧崋
戞1晅榐乽妛廗僾儔儞恌抐Test乿
|
P.4丂栤俀
|
栤俀偺崌寁嬥妟偺夝愢傪偍婅偄偟傑偡丅
|
杮栤戣偼弮戝棨幃偲側偭偰偄傞偺偱丄奐巒巆崅姩掕傪梡偄偰巇栿傪偡傞偨傔丄奐巒巇栿偑埲壓偺傛偆偵側傝傑偡丅
乹奐巒巇栿乺
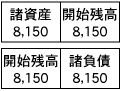
乹怳懼巇栿乺

乹婜拞庢堷偺嬥妟乺
4,800亄7,800亄4,200亄1,800亄245亄500亄 50(棙塿弨旛嬥愊棫妟)亄100亄245亄500亄2,100亄50亄15亖22,405
偟偨偑偭偰
8丆150亄8丆150亄60亄5亄22丆405亖38丆770
偲側傝傑偡丅
|
|
2010擭10寧崋
|
P.127⑥強桳尃堏揮奜儕乕僗帒嶻偺尭壙彏媝丂崙奜儕乕僗帒嶻偵偮偄偰
|
P.127⑥強桳尃堏揮奜儕乕僗帒嶻偺媽崙奜儕乕僗婜娫掕妟朄傪巊梡偡傞応崌偺儕乕僗帒嶻偺戄偟庤懁偲庁傝庤懁偺張棟乮尭壙彏媝偺曽朄乯偵偮偄偰偛幙栤偝偣偰偔偩偝偄丅
戄偟庤懁偐傜偺幙栤
暯惉20擭3寧31擔埲慜
媽崙奜儕乕僗婜娫掕妟朄偱彏媝偡傞偲偁傞偺偱偡偑丄偙偪傜偼攧攦張棟偱偼側偔捓戄張棟偲側傞偺偱偟傚偆偐丅
暯惉20擭4寧 1擔埲崀
暯惉20擭3寧31擔埲慜偺尭壙彏媝偼媽崙奜儕乕僗婜娫掕妟朄偵傛偭偰張棟偟偰偍傝傑偟偨偑丄暯惉20擭4寧1擔埲崀偺尭壙彏媝偼丄儕乕僗婜娫掕妟朄偵曄峏偟偰彏媝偡傞偺偱偟傚偆偐丅偦傟偲傕丄媽崙奜儕乕僗婜娫掕妟朄偺傑傑張棟偡傞偺偱偟傚偆偐丅
庁傝庤懁乮奜崙朄恖乯偐傜偺幙栤
暯惉20擭3寧31擔埲慜
奜崙朄恖偑峴偆儕乕僗帒嶻偺尭壙彏媝偺張棟偼偳偺傛偆偵側傞偺偐丅
暯惉20擭4寧 1擔埲崀
奜崙朄恖偑峴偆儕乕僗帒嶻偺尭壙彏媝偺張棟偼偳偺傛偆偵側傞偺偐丅
|
儕乕僗帒嶻
暯惉20擭4寧侾擔埲屻宊栺掲寢偺儕乕僗帒嶻偼攧攦埖偄偲偝傟傑偡偺偱丄崙撪偵偍偗傞庁庤懁偱偺尭壙彏媝偲側傝丄乽儕乕僗婜娫掕妟朄乿偑嫮惂偝傟傑偡丅傑偨丄暯惉20擭3寧31擔埲慜偺傕偺偼捓戄偺庢埖偄偲偟偰丄戄庤懁偱捠忢偺尭壙彏媝傪偡傞偙偲偲偝傟偰偄傑偡丅
崙奜儕乕僗帒嶻
暯惉20擭3寧31擔埲慜偵偮偄偰偺崙奜儕乕僗帒嶻偵偮偄偰偩偗偼丄戄庤懁偱乽媽崙奜儕乕僗婜娫掕妟朄乿偑嫮惂偝傟偰偄傑偡丅傑偨丄宊栺掲寢擔偱庢埖偄偑曄傢傝傑偡偐傜丄暯惉20擭3寧31擔埲慜宊栺掲寢偺傕偺偼偢偭偲媽偺傑傑偺庢埖偄偵側傝傑偡丅
嵟屻偵
崙奜偵偁傞奜崙朄恖偺儕乕僗帒嶻偵偮偄偰偼擔杮偺朄恖惻朄偼揔梡偝傟偢丄偦偺奜崙偺惻朄偵婎偯偔尭壙彏媝傪偡傞偙偲偲側傝傑偡丅
戄庤丒庁庤偺偳偪傜偱尭壙彏媝傪偡傞偺偐丄朄恖惻朄偺巤峴抧偼擔杮崙撪偵尷傞偙偲側偳傪偍偝偊偰丄偟偭偐傝儅僗僞乕偟偰壓偝偄偹丅
|
|
2010擭9寧崋
|
僴僀僷乕丒僩儗乕僯儞僌朄恖惻朄P.121夝摎
嵍懁丂忋偐傜2峴栚
乽擺惻廩摉嬥偐傜巟弌偟偨帠嬈惻摍偺妟乿
|
乽擺惻廩摉嬥偐傜巟弌偟偨帠嬈惻摍偺妟丂168,135,000墌乿 偺嬥妟偼偳偺傛偆偵摫偒弌偣傞偺偐丅棟桼偲偦偺夁掱傪嫵偊偰偔偩偝偄丅
|
1.乵慜婜妋掕怽崘乶偺惻柋張棟偮偄偰偼丄夝愢侾偱傕偁傝傑偡傛偆偵乽擺惻廩摉嬥偐傜巟弌偟偨帠嬈惻摍偺妟47,510,000墌乮尭嶼丒棷曐乯乿偲側傝傑偡丅
弮妟昞帵偺張棟偱偡丅
2丏乵摉婜拞娫怽崘乶偺惻柋張棟偱偡偑丄弮妟昞帵偺張棟偱偼側偔丄憤妟昞帵偺張棟傪偟偰偍傝傑偡丅杮帍119儁乕僕偺3②乮僴乯偺惻柋張棟偲摨條偵丄師偺偲偍傝偺張棟傪偍偙側偭偰偄傑偡丅
擺惻廩摉嬥栠擖塿擣梕丂120,625,000墌乮尭嶼丒棷曐乯
懝嬥寁忋朄恖惻丂75,960,000墌乮壛嶼丒棷曐乯
懝嬥寁忋廧柉惻丂8,205,000墌乮壛嶼丒棷曐乯
3丏忋婰偺乽擺惻廩摉嬥栠擖塿擣梕丂120,625,000墌乮尭嶼丒棷曐乯乿偲乵慜婜妋掕怽崘乶偺乽擺惻廩摉嬥偐傜巟弌偟偨帠嬈惻摍偺妟47,510,000墌乮尭嶼丒棷曐乯乿偲偺崌寁妟傪傑偲傔偰乽擺惻廩摉嬥偐傜巟弌偟偨帠嬈惻摍偺妟168,135,000墌乮尭嶼丒棷曐乯乿偲夝摎偵偍偄偰偼昞帵偝傟偰偍傝傑偡丅
場傒偵丄拞娫暘偺乽懝嬥寁忋朄恖惻乿媦傃乽懝嬥寁忋廧柉惻乿偼偦傟偧傟乵摉婜慜3帠嬈擭搙偺廋惓怽崘乶偺朄恖惻妟媦傃廧柉惻妟偲崌嶼昞帵偝傟偰偄傑偡丅
杮棃偼丄乵摉婜拞娫怽崘乶偺惻柋張棟偼丄旓梡張棟偐壖暐宱棟張棟偑堦斒揑偱丄擺惻廩摉嬥張棟偼椺奜揑側張棟偵側傝傑偡丅
(拲)丂慜婜暘偺擺惻廩摉嬥偐傜巟弌偟偨帠嬈惻摍偺妟乿偲乽摉婜偺拞娫暘丂擺惻廩摉嬥栠擖傟塿擣梕偺妟乿傪崌寁偲偟偨嬥妟傪乽擺惻廩摉嬥偐傜巟弌偟偨帠嬈惻摍偺妟乿偲偟偰偁傝傑偡偑丄昁偢偟傕崌嶼偟側偗傟偽側傜側偄偲偄偆偙偲偼偁傝傑偣傫丅屄乆偵昞婰偟偰傕壗傜嵎偟巟偊偁傝傑偣傫丅幚柋忋偼丄崌嶼偡傞偙偲偑懡偄傛偆偱偡丅
乽擺惻廩摉嬥偐傜巟弌偟偨帠嬈惻摍偺妟乿偼丄惓幃偵偼朄恖惻朄巤峴婯懃偺暿昞巐偵偍偄偰乽擺惻廩摉嬥偐傜巟弌偟偨帠嬈惻摍偺嬥妟乿偲偟偰摿宖偝傟偰偄傑偡偐傜丄擺惻廩摉嬥曽幃偺傕偺偼傑偲傔偰昞婰偟偨曽偑傛偄傛偆偵傕巚傢傟傑偡偑丄屄乆偵昞婰偟偰傕栤戣偼偁傝傑偣傫丅
拞娫暘偲廋惓暘傕崌嶼偟傑偟偨偑丄屄乆偺昞婰偱傕峔偄傑偣傫丅偙傟傕幚柋忋偼崌嶼偡傞偙偲偑懡偄偲巚傢傟傑偡丅
|
|
2010擭3寧崋
8寧崋
|
傎傏摨偠栤戣偵懳偡傞夝朄偵偮偄偰
|
夛寁恖僐乕僗3寧崋乬P.106 楙廗栤戣3丂奜壿寶桳壙徹寯乭偲丄8寧崋乬P.86 俀桳壙徹寯偺乮5乯幍屗幮幮嵚乭偺栤戣偼傎傏摨偠偱偁傞偺偵夝朄偑堘偭偰偄傑偡丅
8寧崋偱偼丄夝摎棑偵乽墌壿寶嵚尃偺張棟偲堎側傝丄彏媝尨壙朄偼揔梡偟側偄乿偲婰嵹偝傟偰偄傑偡偑丄3寧崋偱偼偦偺曽朄傪巊偭偰偄傑偡丅偙偺擇偮偺栤戣偺堘偄偼壗側偺偐丄偛嫵庼偍婅偄偄偨偟傑偡丅
|
①丂8寧崋偺夞摎
敧屗幮幮嵚偺栤戣暥偲斾妑偟偰丄乽庢摼壙妟偲嵚寯嬥妟偲偺嵎妟偼嬥棙偺挷惍偲擣傔傜傟傞巪乿偺巜帵偑側偄偨傔丄彏媝尨壙朄傪揔梡偟側偄偲撉傒庢傞昁梫偑偁傝傑偡丅偁傞堄枴丄庴尡僥僋僯僢僋偱偡丅
偟偨偑偄傑偟偰丄夝愢暥偼丄亀仏墌壿寶嵚尃偺張棟偲堎側傝丄彏媝尨壙朄偼揔梡偟側偄丅亁偱偼側偔丄亀仏敧屗幮幮嵚偺栤戣暥偲斾妑偟偰丄乽庢摼壙妟偲嵚寯嬥妟偲偺嵎妟偼嬥棙偺挷惍偲擣傔傜傟傞巪乿偺巜帵偑側偄偨傔丄彏媝尨壙朄傪揔梡偟側偄偲撉傒庢傞丅亁偲偡傋偒偱偟偨丅
丂3寧崋偺夞摎
乽庢摼壙妟偲嵚寯嬥妟偲偺嵎妟偼嬥棙偺挷惍偲擣傔傜傟丄彏媝尨壙朄(掕妟朄)偵傛傝張棟偡傞丅乿偺巜帵偑偁傟偽丄傛傝挌擩側栤戣暥偱偟偨丅(①偺傛偆偵丄2偮偺幮嵚偺張棟傪斾妑偝偣傛偆偲偟偨栤戣偱側偄偙偲傪峫偊傟偽丄庴尡幰偺怺偄棟夝傪栤偆偙偲偺偱偒傞丄彏媝尨壙朄(杮栤偐傜媄弍揑偵壜擻側掕妟朄)傪揔梡偝偣傞栤戣偱偁傞偙偲偑懡偄偱偡)丅
|
|
2010擭7寧崋
|
僞僢僋僗丒僿僀僽儞惻惂偵偮偄偰
|
侾丏乽揔梡懳徾嬥妟乿偵娭偟偰
乮侾乯P.130(5)偵乽揔梡懳徾嬥妟亖婎弨強摼嬥妟乕乮擺晅朄恖強摼惻偺妟亄慜7擭埲撪偺孞墇寚懝嬥乯乿
偲偁傝傑偡偑丄
乽婎弨強摼嬥妟乿偺惓妋側掕媊幃偼偛偞偄傑偡偐丅捠忢丄帋尡偱偼栤戣暥拞偵梌偊傜傟傞傕偺側偺偱偟傚偆偐丅
乮俀乯乽擺晅朄恖強摼惻乿偱偡偑丄P.131偺椺戣偱偼丄戞12婜暘乮慜婜乯偺奜崙朄恖惻傪峊彍偟偰偍傝丄
13婜乮摉婜乯偺7,200,000墌偱偼側偄傛偆偱偡偑丄偙傟偼忢偵慜婜偺擺晅朄恖惻側偺偱偟傚偆偐丠
俀丏乽帒嶻惈強摼偺嬥妟乮摿掕強摼偺嬥妟乯乿偵娭偟偰
乮侾乯嬶懱揑偵偼丄P.131偺①乣④傪巜偡偲巚傢傟傑偡偑丄堦尵偱偄偊偽偳偆偄偭偨傕偺傪
僀儊乕僕偡傟偽傛偄偱偟傚偆偐丅乽堦掕偺攝摉丒棙巕丒巊梡椏摍偺晅偗懼偊偺偍偦傟偺崅偄傕偺乿偲偺偛愢柧偑偁傝傑偡偑丄乽晅偗懼偊偺偍偦傟偺崅偄乿偲偼偳偆偄偭偨傕偺偱偟傚偆偐
|
侾丏
乮侾乯乽婎弨強摼嬥妟乿偺掕媊偱偡偑丄慬抲朄66忦偺俇戞2崁擇崋乮掕媊乯偺乽揔梡懳徾嬥妟乿偺拞偵婯掕偝傟偰偄傑偡丅傢偑崙偺惻朄偵傛傞強摼偺嬥妟偺寁嶼偵傛傞偐丄偦偺摿掕奜崙巕夛幮摍偺寛嶼偵婎偯偒丄偦傟偵堦掕偺挷惍傪壛偊偨傕偺偵傛傞偐偼宲懕傪忦審偵慖戰揔梡偝傟傑偡丅幚柋忋偼旕忢偵擄偟偄寁嶼偵側傝傑偡偺偱丄惻棟巑帋尡偵偍偄偰偼昁偢梌偊傜傟傞偲巚偄傑偡丅偙偺寁嶼偑弌戣偝傟傑偡偲丄偲偰傕2帪娫埲撪偵偼廔椆偟側偄偱偟傚偆偐傜偹丅
乮俀乯乽擺晅朄恖強摼惻偺妟乿偱偡偑丄擺晅妋掕儀乕僗偱偡偐傜丄昁偢慜婜偺傕偺偑懳徾偵側傝傑偡丅摉婜偺朄恖強摼惻偺妟偼怽崘擺惻曽幃偱偡偐傜丄梻婜偵擺晅偑妋掕摓棃偡傞偙偲偵側傝傑偡偐傜丄堦婜偢偮僘儗偑惗偠傞偙偲偲側傝傑偡丅偦傟偵懳偟偰丄巟暐攝摉摍偺妟偼丄妋掕偟偨傕偺偵尷傜傟傑偡偑丄摿掕奜崙巕夛幮摍偺帠嬈擭搙廔椆偺擔埲屻俀寧傪宱夁偟偨擔傪娷傓撪崙朄恖偺帠嬈擭搙廔椆偺擔傑偱偵妋掕偟偰偄傟偽傛偄偲偝傟偰偄傑偟偨乮媽慬抲朄捠払66偺俇亅俇乯丅奜崙巕夛幮攝摉塿嬥晄嶼擖惂搙偺摫擖偵敽偄丄忚梋嬥偺攝摉摍偼峊彍偝傟側偄偙偲偲側傝傑偟偨偐傜丄乽揔梡懳徾棷曐嬥妟乿偲偼偄傢側偔側傝傑偟偨丅
俀丏
乮侾乯乽晅偗懼偊偺偍偦傟偺崅偄乿傕偺偵偮偄偰丄偛愢柧偟傑偡丅懡崙愋婇嬈偺僌儖乕僾朄恖偼丄僞僢僋僗丒僾儔僯儞僌傪偟偰忢偵僌儘乕僶儖偱懝塿傪峫偊偰偄傑偡丅惻棪偺掅偄崙傊強摼傪晅偗懼偊傞偙偲偼擔忢拑斞帠偱偡丅堏揮壙奿惻惂摍偱婯惂偟偰偄傑偡偑丄惓捈丄惻惂揑偵偼捛偄偮偄偰偄側偄偺偑尰忬偱偼側偄偱偟傚偆偐丅崙嵺惻柋偵廬帠偝傟傞偲懡暘傃偭偔傝偝傟傞偙偲偲巚偄傑偡丅乽晅偗懼偊偺偍偦傟偺崅偄乿傕偺偲偼丄彂椶忋偱梕堈偵堏揮偺偱偒傞傕偺偱偁偭偰丄岺嬈強桳尃偲偐挊嶌尃偲偐柍宍屌掕帒嶻側偳偑峫偊傜傟傑偡偹丅搚抧丒寶暔摍偺晄摦嶻偼偝偡偑偵晅偗懼偊偑偒偒傑偣傫傛偹丅
|
|
2006擭2寧崋暿嶜晅榐
|
曤婰榑庛揰敪尒両栤戣廤乮墳梡榑揰曇乯
|
楢寢夛寁偑傛偔棟夝偱偒傑偣傫丅婎杮彂偑偁偭偨傜嫵偊偰偔偩偝偄丅
|
妛峑傪棙梡偟偰偄傞応崌偼丄攝晍偝傟傞僥僉僗僩偱妛廗偡傟偽傛偄偲巚偄傑偡丅撈妛偺応崌偵偼擔彜曤婰1媺偺僥僉僗僩乮彜嬈曤婰丒夛寁妛乯偑嶲峫偵側傞偲巚偄傑偡丅惻棟巑帋尡偵尷傟偽丄楢寢夛寁帺懱弌戣偺壜擻惈偑偦傟傎偳崅偔側偄偲巚傢傟傑偡偺偱丄5寧崰偵妛廗偟偰傕栤戣側偄偲巚偄傑偡丅
|
|
2006擭2寧崋
|
戞111夞擔彜曤婰専掕帋尡1媺丂栤戣偲柾斖夝摎丒夝愢p.75偺塃壓
|
攦妡嬥姩掕偵偼堊懼嵎塿555偼峫椂偟側偄偺偱偡偐丠
|
p.75偺攦妡嬥姩掕偼丄A彜昳偺巇擖崅傪悇掕偡傞偨傔偵丄寛嶼廋惓慜偺帠崁偵婎偯偄偰曋媂揑偵嶌惉偟偨傕偺偱丄夝摎偺庤弴傪棟夝偟偰傕傜偆偨傔偺傕偺偱偡丅嵟廔揑偵偼乮寛嶼廋惓婰擖屻偲偄偆堄枴偱乯丄偛幙栤偺傛偆偵堊懼嵎塿傪峫椂偟側偗傟偽側傝傑偣傫丅
|
|
2006擭1寧崋暿嶜晅榐
|
曤婰榑庛揰敪尒両栤戣廤p.56摿庩彜昳攧攦丒栤戣5枹拝昳偺張棟偺巇曽
|
帒椏?偺慜T/B偲帒椏?(4)俁傛傝枹拝昳偺婜庱巆崅1,300,000墌摉婜峸擖崅2,400,000乮慜T/B3,700,000亅1,300,000乯慜婜孞墇暘偺1,300,000墌偑尰暔傪庴偗擖傟偨偙偲偵傛傝巇擖姩掕偵怳傝懼偊傜傟丄摉婜峸擖崅偑婜枛巆崅偲偟偰P/L偺婜枛彜昳扞壍崅偵嶼擖偝傟偰偄傞傛偆偱偡偑丄慜T/B偺枹拝昳攧忋5,300,000墌偵懳偡傞尨壙憡摉妟偼偳偺傛偆偵峫偊傟偽傛偄偺偱偟傚偆偐丠厱i偼堦斒斕攧偲摨偠棙塿棪偱偁傞苽處w帵偵傛傝丄帋梡斕攧偺尨壙棪偑0.7偱偁傞偐傜丄枹拝昳偺尨壙棪偼0.7/1.2偲側傝丄枹拝昳攧忋5,300,000亊0.7/1.2偑尨壙憡摉妟偵側傞偲巚偆偺偱偡偑丄偦偆偡傞偲枹拝昳姩掕偺戄庁偑堦抳偟側偄偙偲偵側傝傑偡丅峫偊曽傪嫵偊偰偔偩偝偄丅
|
侾丏枹拝昳攧忋5,300,000墌偵偮偄偰枹拝昳姩掕傪尭彮偝偣傞働乕僗偼丄(1)尰暔傪庴偗擖傟偨偲偒丄(2)慏壸徹寯傪揮攧偟偨偲偒偺2偮偲側傝傑偡丅夛寁張棟偼偲傕偵巇擖姩掕乮嶰暘妱朄偺偲偒乯偵怳傝懼偊傑偡丅傛偭偰丄5,300,000墌偺枹拝昳攧忋偵懳墳偡傞尨壙偼巇擖姩掕偺拞偵娷傑傟偰偄傞偙偲偵側傝傑偡丅俀丏枹拝昳偺尨壙憡摉妟偵偮偄偰寢榑偐傜怽偟忋偘傞偲丄枹拝昳乮堦斒斕攧乯偺尨壙棪傪寁嶼偡傞昁梫偼杮棃偁傝傑偣傫丅偟偐偟丄尨壙晹暘傪暘棧偡傞偙偲偑偱偒側偄偺偱丄堦斒斕攧傗枹拝昳傕娷傔偰尨壙棪傪寁嶼偡傞偙偲偵側傝傑偡丅幙栤偱偼乽0.7/1.2乿偲偄偆暘悢偱枹拝昳偺尨壙棪傪帵偟偰偄傑偟偨偑丄乽0.7乿偲偄偆尨壙棪偼乽尨壙乛帋梡攧壙乿偲帵偡偙偲偑偱偒傑偡丅傛偭偰丄枹拝昳攧壙傪帋梡攧壙偵偡傞偵偼1.2攞偡傟偽傛偄偺偱丄5,300,000亊1.2亖6,360,000乮帋梡攧壙儀乕僗乯6,360,000亊0.7亖4,452,000乮枹拝昳偺尨壙乯偲側傝傑偡丅
|